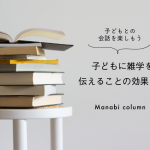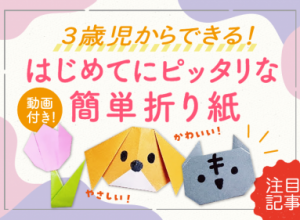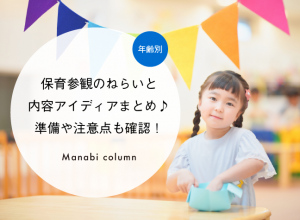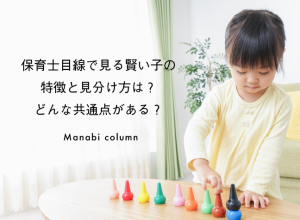保育の導入とは何?おすすめのネタや実践例&意識したいポイント5つをご紹介!
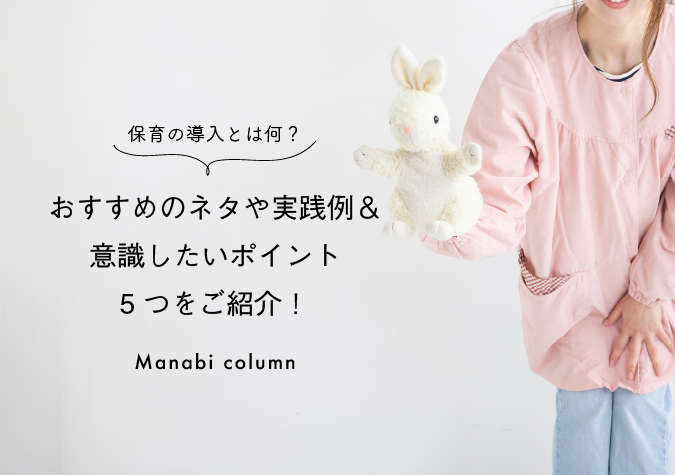
保育の導入は必要なの?何をすればいいかよくわからない…そんな疑問や悩みを抱えている実習生のみなさんへ、保育の導入について簡単解説します。保育実習で使えるおすすめの導入ネタを年齢別に、そしてイメージをもちやすいよう実践例もご紹介していきます。
index
1. 保育の導入とは?意味を簡単解説!
2. 年齢別おすすめの導入ネタ+実践例
【手遊び】導入の定番
年齢別おすすめ手遊び
手遊びを導入に使った実践例
【ペープサート】視覚的に惹きつける
年齢別おすすめペープサート
ペープサートを導入に使った実践例
【絵本】活動へイメージをつなげる
年齢別おすすめ絵本
絵本を導入に使った実践例
【お話・言葉】話術で惹きつける
年齢別おすすめのお話
お話を導入に使った実践例
3. 保育の導入で意識したいポイント5つ
①主活動とのつながりを意識する
②年齢、発達に合った導入を取り入れる
③楽しい雰囲気を作る
④導入のボリュームに注意する
⓹子どもの反応を見ながら進める
4. 保育実習の園探しもできる「ほいコレナビ」をチェック♪
1. 保育の導入とは?意味を簡単解説!
保育の導入とは何か?
その意味は「次の活動に向けて子ども達の気持ちを導くためのアクション」です。
もしも導入をやらずに突然活動を始めてしまったらどうなるでしょうか?
子どもたちは突然の活動に戸惑い、
理解や興味が深まらず活動を始めることになるかもしれません。
一方で、活動前に導入を取り入れると子どもたちは「これから何をするの!?」とワクワクするでしょう。
活動へのイメージがつながると内容も理解しやすくなり、活動がスムーズに進みます。
2. 年齢別おすすめの導入ネタ+実践例
【手遊び】導入の定番
手遊びは道具がいらないので、さまざまなシーンで取り入れられます。
年齢に合った手遊びをいくつか覚えておきましょう。
年齢別おすすめ手遊び
0歳児~
・むすんでひらいて
・いとまき
・あたまかたひざぽん
0歳児クラスには、テンポがゆったりで振りも簡単な手遊びがおすすめ。
1、2歳児~
・とんとんとんとんひげじいさん
・グーチョキパーでなにつくろう
・きゃべつのなかから
1,2歳児クラスでは、指先をたくさん動かすような手遊びがおすすめ。
3歳児~
・やきいもグーチーパー
・いっぽんゆびのはくしゅ
3歳児クラス以降は、ゲーム要素や繰り返しの中で変化を楽しめるような手遊びがおすすめ。
手遊びを導入に使った実践例
【対象】1~2歳児
【導入】手遊び「あたまかたひざぽん」
【次の活動】絵本読み聞かせ
【進め方】
手遊びの最後「て は○○」のフレーズに合わせてからだのパーツに触れて楽しむ。
♪あたまかたひざぽん ひざぽん ひざぽん〜…てはおみみ!…てはおくち!… てはおめめ!
「てはおめめ」で眼鏡のように両手を丸めたポーズをする。
「あ!みんなとってもいいおめめだね〜!」
「今日はこれから先生がみんなに絵本を読もうと思っているんだけど、そのままいいおめめで見られるかな?」
子どもたちの意識が絵本に向いたら読み聞かせにうつる。
【ペープサート】視覚的に惹きつける
ペープサートは、視覚的な効果で子どもの興味を惹きつけやすい導入ネタ。
学生のうちに作成しておくと、実習だけでなくその後の仕事にも役立つアイテムです。
年齢別おすすめペープサート
0歳児~
「いないいないばあ」
表面に顔を隠した動物、裏面に「ばあ」と手を開いて顔を見せた動物を描く。
動物だけでなく、ママ、パパ、あかちゃんなどで作るのもおすすめ♪
1,2歳児~
「こぶたたぬききつねねこ」
4面それぞれに動物を描き、歌に合わせて返しながらペープサートを見せる。
1,2歳児クラスでは、一緒に歌いながら楽しめるペープサートがおすすめ。
3歳児~
「シルエットクイズ」
表面にシルエット、裏面に答えとなるものを描いてクイズ形式で楽しむ。
3歳児クラス以降は、クイズ性のあるペープサートにすると盛り上がります。
ペープサートを導入に使った実践例
【対象】3~5歳児
【導入】ペープサート「シルエットクイズ」
【次の活動】〇△☐鬼(かたち鬼)
【進め方】
ペープサートで「シルエットクイズ」を楽しむ。
「シルエットクイズは難しかった?」
「今出てきた〇△☐のゲームをみんなでやろうと思っているんだけれど、どうかな?」
戸外に移動して、〇△☐鬼の説明と準備にうつる。
※〇△☐鬼(かたち鬼)遊び方↓
〇△☐の形を園庭に描き、鬼を決める。
鬼は〇△☐のどれか一つを選んで大きな声で言う。
鬼以外は鬼の指定した形の中に逃げ込む。
鬼は形の中には入れないが、形の外でタッチできたら鬼は交代できる。
【絵本】活動へイメージをつなげる
絵本による導入は、視覚的な効果で次の活動へイメージをつなげやすくなります。
手遊びと組み合わせながら、次の活動に関連するテーマの絵本を取り入れると効果的です。
年齢別おすすめ絵本
まねっこ遊びの導入におすすめ♪
いもむしのようにゴロゴロしてまねっこを楽しみましょう。
1,2歳児~
おみせやさんごっこの導入におすすめ。
自由遊びの中でおみせやさんごっこを楽しみましょう。
製作の導入におすすめ。
絵のテーマにしてもいいですね。
絵本を導入に使った実践例
【対象】4~5歳児
【導入】手遊び「いっぽんゆびのはくしゅ」
【次の活動】折り紙製作「こびとさん」
【進め方】
手遊びと絵本の後、内容を子どもたちと振り返る。
「みんなのお腹やお口にもこびとさんが住んでいるかな?」
「どんなこびとさんだと思う?」
子どもたちと対話してイメージを膨らませたら、折り紙製作の見本を見せる。
「今日はみんなもこびとさんを折り紙で折ってみようか!」
折り紙製作の準備、説明にうつる。
【お話・言葉】話術で惹きつける
お話での導入は難易度が高めですが、保育者としては必要なスキル。
話を聞いてもらいたい場面での子どもの注意や、
もっと先生と話したい!という気持ちを引き出せるかもしれません。
年齢別おすすめのお話
3歳児~
・今日の朝ごはんの話
・先生の好きな物は○○クイズ
子どもたちがイメージしやすいよう、身近なテーマを取り上げたお話がおすすめです。
4,5歳児~
・クイズ
・ちょこっと雑学
子どもたちの好奇心や探求心をくすぐる内容がおすすめです。
乳児クラスは視覚的に効果のあるものを交えながら話す方が理解しやすいでしょう。
また、子どもに質問したり反応を確認したりしながら進めるといいですね。
お話を導入に使った実践例
【対象】4~5歳児
【導入】お話
【次の活動】散歩
【進め方】
導入としてお話を始める。
「みんなにクイズ!ハートの形の葉っぱが集まっている植物ってなんだ⁉」
「正解は…クローバー!みんな見たことある?知っているかな?」
クイズから始まり、クローバーにまつわる雑学を紹介する。
「今日はみんなでクローバー探しをしにお散歩にでかけよう!」
散歩の活動につなげる。
3. 保育の導入で意識したいポイント5つ
①主活動とのつながりを意識する
導入の役割は、子どもたちの興味を高めたりイメージを膨らませたりすること。
効果的な導入を取り入れ、次の活動を展開させていきましょう。
②年齢、発達に合った導入を取り入れる
年齢や発達により子どもたちの興味の示し方や理解度には違いがあります。
年齢や発達に合っていない導入は子どもの集中力が続かず、
逆効果となるので注意しましょう。
③楽しい雰囲気を作る
楽しい雰囲気が作れると、子どもたちは「次は何をやるのかな!?」とワクワクし、
次の活動も盛り上がりやすくなります。
④導入のボリュームに注意する
導入が主活動のようなボリュームになってしまうと、
次の活動まで子どもたちの集中力や興味がもたないことがあります。
逆効果となるので注意しましょう。
⓹子どもの反応を見ながら進める
導入の目的は主活動に向けて気持ちを導くこと。
子どもの様子によってその長さや内容を変えられるといいですね。
子どもの反応を見ながら保育を組み立てることは、保育者に必要なスキルです。

4. 保育実習の園探しもできる「ほいコレナビ」をチェック♪
いかがでしたか?
今回は、保育の「導入」をテーマに取り上げました。
ほいコレinfoでは、他にも保育実習に役立つ記事をたくさん紹介しています。
知りたい情報がきっと見つかるはず♪
また、ほいコレナビでは保育実習の園探しをすることもできます。
ぜひチェックしてみてくださいね♪

執筆者:たか 先生(保育教諭1)