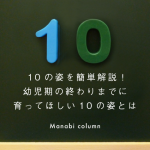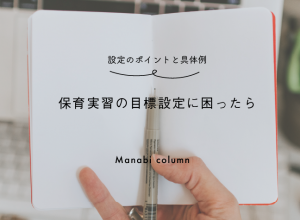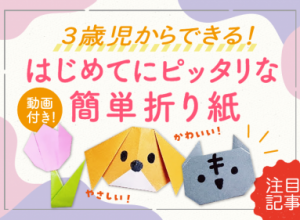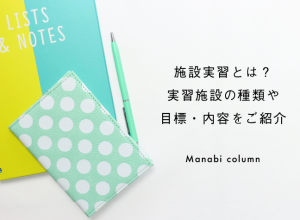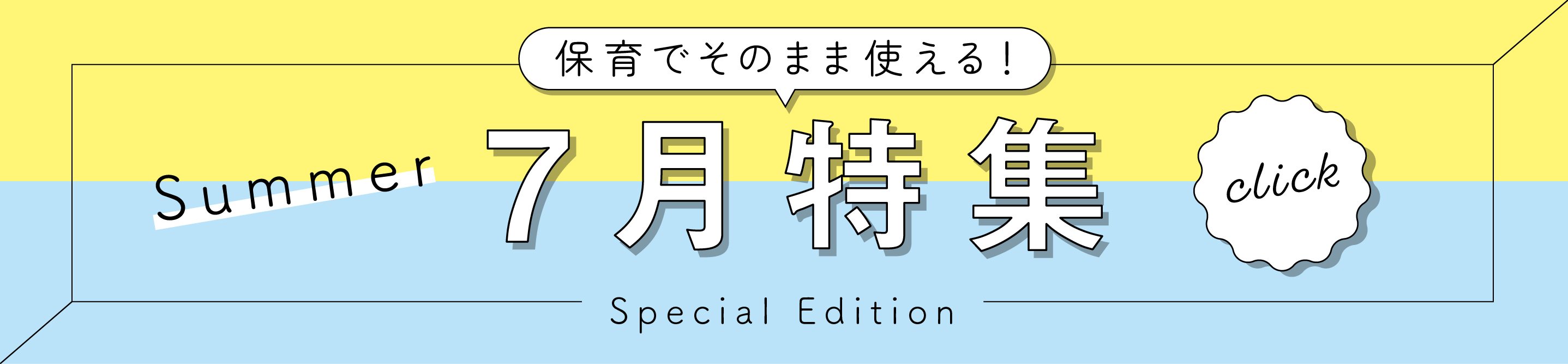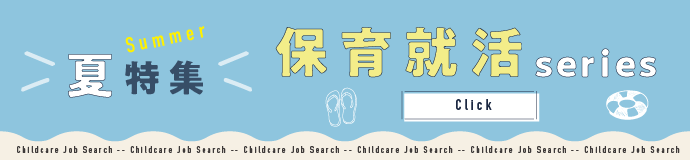【保育】 非認知能力 ってなに?保育の中で意識したいポイントは?
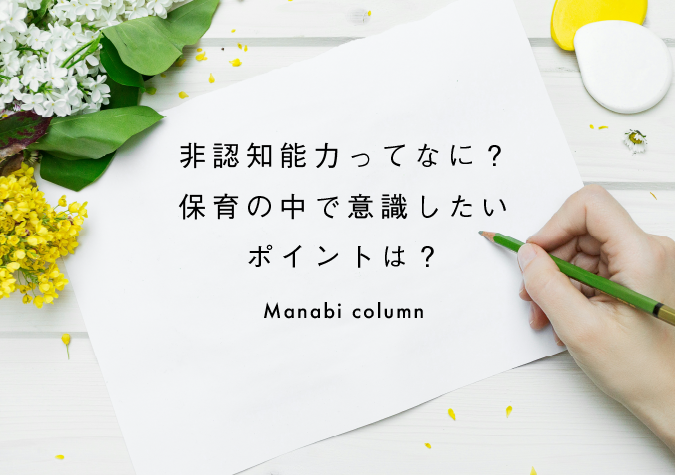
『 非認知能力 』とは何か知っていますか?聞いたことはあるけれどよくわからないという方は必見!保育に関係する大切なキーワード『 非認知能力 』について簡単解説します。保育の中で意識したいポイントもまとめましたのでぜひ参考にしてみて下さい♪
index
1.『 非認知能力 』ってなに?
2. 非認知能力 はどのようにして身につくの?
3. 非認知能力 を育む!保育の中で意識したいこと
◆子ども自身を認める関わり
◆他者と関わる機会を作り見守る
◆興味関心が高まるような環境作り
1.『 非認知能力 』ってなに?
ほいコレでは、保育に役立つ情報をたくさん発信中!
今回のテーマは、『 非認知能力 』。
『 非認知能力 』は、保育に関係する大切なキーワードです。
非認知能力 とは
『社会情緒的スキル』とも呼ばれ、
意欲や、自信、自己コントロールする力、思いやり、協調性など、
学力テストやIQで表されるような認知能力(知識力)とは違ったものを、
『 非認知能力 』といいます。
2000年ノーベル経済学賞受賞者の経済学者ジェームズ・J・ヘックマンらの研究により、
幼児期から 非認知能力 を育むことの重要性が注目されるようになりました。
非認知能力 は、『生きる力』のベースとなるもので、
色々なことに意欲を持って取り組んだり、
行き詰った時に気持ちや考え方を切り替えたりして、
将来の生活を心豊かに過ごすためには大切な力です。
また、認知能力と 非認知能力 は全く別のものという訳でなく、
関係しあいながらそれぞれ育っていくもの。
興味関心をもって意欲的に取り組む(非認知)中で、
色々な知識を学んでいく(認知)というようなことです。
2. 非認知能力 はどのようにして身につくの?
非認知能力 は、特別なトレーニングや活動をすることで育まれるという訳でなく、
日常生活の体験や経験によって徐々に身についていくもの。
乳幼児期では何より『遊び』が 非認知能力 を身につけていく上で重要となります。
『遊び』は、子ども自身の興味関心から始まり、
夢中になって取り組んだり、楽しさや嬉しさを感じたりする場です。
幼児期になると、ルールを理解して遊ぼうとしたり、
友達と関わりながら色々な経験をしたりするきっかけにもなります。
乳幼児期では、この遊びを充実させることが、
非認知能力 を育む一番の方法といえるでしょう。
また、2018年に保育・幼児教育に関する共通の目標として、
『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』( 10の姿 )が示されました。
保育の場でも 非認知能力 を伸ばすことを意識した関わりが大切なのです。
3. 非認知能力 を育む!保育の中で意識したいこと
子ども達の 非認知能力 を育んでいくには、
保育者はどのような意識を持つ必要があるのでしょうか。
関りや活動のポイントをまとめてみました。
非認知能力 を育む保育のポイント
・子ども自身を認める関わり
・他者と関わる機会を作り見守る
・興味関心が高まるような環境作り
◆子ども自身を認める関わり
まず何よりも、子ども一人ひとりの存在を認めて寄り添うことで、
自己肯定感や自信を高めていくことが大切です。
「○○ちゃんのこんなところがステキだね。」
など、子ども達の姿を具体的に取り上げてほめたり、
いつも素敵な姿を見ているよと伝えることで、
子ども達の安心や自信、そして意欲にもつながっていくと思います。
身近な大人が他の人の良いところをたくさんほめる姿を見ていると、
子ども達同士でも良いところを認め合えるようになり、
自分のことも、相手のことも大切にしようとする気持ち、思いやりにつながっていくでしょう。
◆他者と関わる機会を作り見守る
非認知能力 の一つとされる協調性に関しても、
自分の思いや考えだけを通そうとするのではなく、
相手の思いや考えにも耳を傾けようとできなければ上手くいきません。
保育の中で集団遊びやルールのある遊びなどを取り入れたり、
一つのことをみんなでやり遂げたりする機会を作れると良いでしょう。
子ども達は、自分以外の人との関わりの中で、
成功や失敗の体験をしたり、葛藤を感じたりすると思います。
保育者は身近な大人の一人として子どもの思いを聞き、
「○○ちゃんはそう感じたんだね。」
「こんな風に話してみると良いかもしれないね。」
など、共感したり提案したりしながらサポートしていけると良いですね。
◆興味関心が高まるような環境作り
子ども達が色々なことに興味関心を持ち、
もっと知りたい!もっと遊びたい!
という気持ちになれるような環境作りを心掛けましょう。
例えば、園外に出掛けて自然に触れ、見つけた花や虫を調べるという活動では、
子ども達の「コレ面白い!」から発見や疑問につながり、
「もっと知りたい!」という探求心が高まっていくこともあるでしょう。
非認知能力 の一つでもある意欲は、興味関心とつながっています。
特に遊びを中心として、子ども達が主体的に活動できるような保育を意識できると良いですね。
いかがでしたか?
今回は、保育に関係する大切なキーワードである『 非認知能力 』について取り上げました。
言葉だけ聞くと難しそうに感じますが、
非認知能力 は、充実した遊びや生活の中で育まれていくということを改めて認識し、
日頃の保育の参考にしていただければと思います。

↓こちらの記事もおすすめ♪
執筆者:たか 先生(保育教諭1)