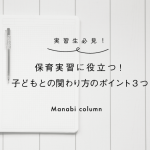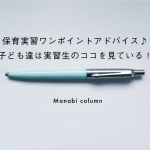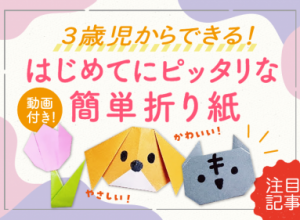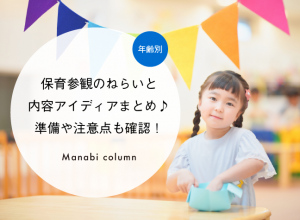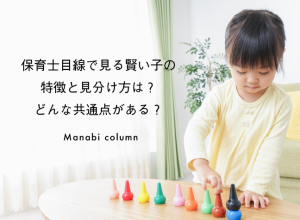【実習生必見】保育実習って何を聞けばいい?すぐに使える質問5選
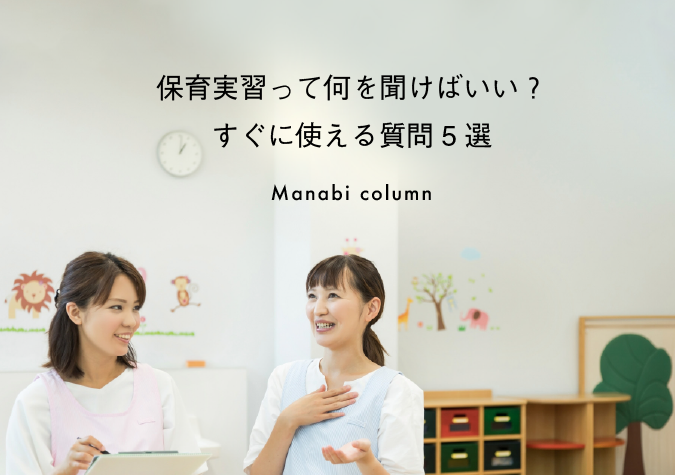
保育実習で質問が思いつかず、困ったことはありませんか? 保育士や子どもの動きを見るのに精一杯で、なかなか質問を考える余裕も無いですよね。 この記事では実習ですぐに使える質問例文を記載していきます。 ぜひ実習で活かしてみてくださいね!
index
1.保育実習における質問の重要性
2.保育実習で質問をするタイミング3選
①反省会
②午睡中
③活動の切れ間
3.すぐに使える質問例文5選
①保育目標やねらい、主活動を教えてください。
②集まり等子どもたちに話をするときに心がけていることはありますか?
③このようなとき先生ならどのように対応されますか?
④読み聞かせの絵本を選ぶポイントを教えてください。
⑤保護者対応で心がけていることはありますか?
4.保育実習で積極的に質問して実りある実習にしよう!
1.保育実習における質問の重要性
保育実習中は、保育の流れや保育士、子どもの動きを把握するだけでも精一杯になりがちですよね。
しかし、実習中に疑問に思ったことや気になったことを積極的に質問することで、さらに深い学びを得られますよ。
保育士として働き出すと、なかなかゆっくり先輩に話を聞く時間が取れません。
実際に保育士として働く先輩たちの話をゆっくり聞けるのも実習生の特権ですよ!
実習を受け入れる側の立場になって考えてみても、積極的に質問してくれる実習生の方が印象がいいですよね。
「熱心だからこれも伝えておこうかな」とプラスの情報も得られるかもしれません。
保育実習では積極的に質問してみましょう!
2.保育実習で質問をするタイミング3選
保育実習中、いつ質問すればいいのかタイミングが難しいですよね。
保育実習で質問をするべきタイミングは以下3つです。
質問をするべきタイミング3選
①反省会
②午睡中
③活動の切れ間
一つずつ詳しく説明していきますね。
①反省会
一番質問しやすいのが反省会の時間です。
保育士も反省会として時間を設けているため、時間を気にせずに質問できます。
「質問はありますか?」と質問の時間を設けてくれることも多いです。
しかし、実習最終日等に反省会の時間が設けられている場合もあるので注意が必要です。
反省会までに質問を忘れないよう、気になったことは必ずメモを取るようにしましょう。
また、子どもの怪我やトラブルの対応等、すぐに確認しておきたいことは反省会を待たずに質問するようにしましょう。
②午睡中
午睡中は事務仕事をしている保育士が多いので、質問しやすい時間帯です。
実習生も休憩時間や事務作業になることが多いと思います。
保育士も休憩を回す時間帯なので、午睡時間に入る前に質問したいことがある旨を伝えておくのがおすすめです。
午睡中は時間に限りがあるため、質問はまとめておくようにしましょう!
③活動の切れ間
子どもの怪我やトラブルの対応等、急を要する質問は活動の切れ間に質問しましょう。
ですが、保育士は常に子どもの動きに目を向け、次の動きを考えながら保育をしています。
実習生が活動の切れ間を見極めるのは難しいと思います。
急ぎの質問でない限りはなるべく反省会や午睡中に質問するようにしましょう。

3.すぐに使える質問例文5選
保育実習中の質問が思いつかないこともありますよね。
ここではすぐに使える質問例文以下5選を紹介します。
すぐに使える質問例文5選
①保育目標やねらい、主活動を教えてください。
②集まり等子どもたちに話をするときに心がけていることはありますか?
③このようなとき先生ならどのように対応されますか?
④読み聞かせの絵本を選ぶポイントを教えてください。
⑤保護者対応で心がけていることはありますか?
一つずつ詳しく説明していきますね。
①保育目標やねらい、主活動を教えてください。
保育目標やねらい、その日の主活動を把握した上で実習に入ることで、保育士の配慮や子どもへの働きかけをより深く学べます。
園によって異なりますが、保育目標やねらい等は前日には決まっていることが多いです。
朝は子どもの受け入れや保護者対応等で保育士も忙しいので、前日に確認しておく方がスムーズですよ。
もし可能であれば週案や日案を見せてもらうのもおすすめです!
保育士が保育をする上で準備すること、考えることを学べます。
週案、日案の書き方も学べますね。

②集まり等子どもたちに話をするときに心がけていることはありますか?
一対一での子どもとの関わりと、集団の子どもに対しての関わり方、話し方で配慮する点は異なります。
日々集団の子どもたちをまとめる役割を担っている保育士に、子どもたちの注目を集める話し方や工夫等を聞いてみましょう!
責任実習等で自分自身がクラス全体に向けて話す場面もありますよね。
自分が難しさを感じた部分があれば、質問のときに一緒に伝えましょう。
自分が実際に経験したことにアドバイスをもらえるとさらにスキルアップに繋がりますよ。
③このようなとき先生ならどのように対応されますか?
実習中に自分自身が子どもの対応で困った場面を挙げて、先生ならどう対応するのか聞いてみましょう!
実際に自分がその場面でどう対応したのか、どう感じたのかもあわせて伝えることがおすすめですよ。
実際に現場で働く保育士の子どもとの関わり方や関わる際の配慮を学ぶことで、自分自身の子どもとの関わりの引き出しを増やせます。

保育をする中で、子どもはさまざまな行動をします。
自分の予想外のことが起きることもあるので、いかに子どもへの対応のレパートリーを持っておくかが大切になります。
実習中も自分の子どもへの対応のレパートリーを増やすチャンスですよ。
学べるチャンスを活用していきましょう!
④読み聞かせの絵本を選ぶポイントを教えてください。
季節ものや子どもたちが好きなもの、その日の活動に関連しているもの等絵本を選ぶ際のポイントはさまざまです。
絵本の選び方のポイントや、読み聞かせの場面でなぜその絵本を選んだのか理由を聞いてみましょう!
自分自身が絵本を選ぶ際のヒントになりますよ。
実習中、読み聞かせを担当することもあると思います。
自分が絵本選びで悩んだり、感じたりしたことがあれば、あわせて質問しましょう。
読み聞かせに関連して、絵本を読むスピードや声のテンポ等の工夫も聞いてみるのがおすすめですよ。

⑤保護者対応で心がけていることはありますか?
保育士として働く際、子どもだけでなく保護者対応も重要な仕事の一つとなります。
実習中は子どもとの関わりや保育士の動きを学ぶ時間が中心となり、保護者対応を観察できる時間はあまりありませんよね。
保育士として働きはじめてから保護者対応に難しさを感じる人も多いです。
実習で保育士が保護者対応の際に大切にしていることや気を付けていることを聞いておくことがおすすめですよ。
保護者は十人十色、さまざまな人がいます。
もちろん子どももさまざまな子がいますが、やはり保護者対応は子どもとの関わりとは違う難しさがあります。
子どもへの関わり、保育士としての動きは実習で練習する機会がありますが、保護者対応は練習がありません。
実際に保育士として働き出して保護者対応を始める前に、情報収集しておきましょう!
自分が保育士として働き出す際の心構えができると思います。

4.保育実習で積極的に質問して実りある実習にしよう!
ここまで、保育実習中に質問するタイミングや質問例文を紹介してきました。
質問のタイミングが分からなかったり、質問が思い浮かばなかったりするときにはぜひ活用してくださいね。
保育士として働き出すと、新人とは言え保護者や子どもから見たら他の先輩保育士と同じ存在です。
子どもや保護者との関わり方、保育の進め方、事務作業の方法…
新人保育士の頃は覚えることがたくさんあります。
実習生の立場でも、保育士の卵です。
いつか働き出すときのために、学べるときにたくさん学んでおきましょう。
現場の保育士の姿を見て、質問して、学べる機会はなかなかないですよ。
毎日保育に付いていくだけで精一杯になってしまうかもしれませんが、ぜひ積極的に質問して実りある実習にしてくださいね。
執筆者:ほいコレ 編集部