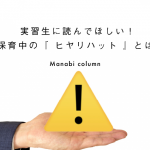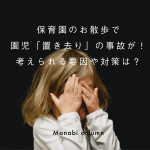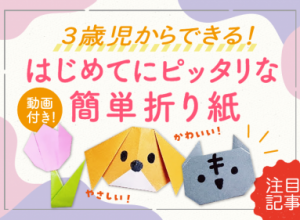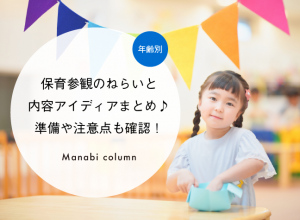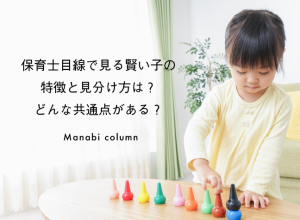【新卒保育士必見】保育中のヒヤリハット対策!すぐに使える対策5選
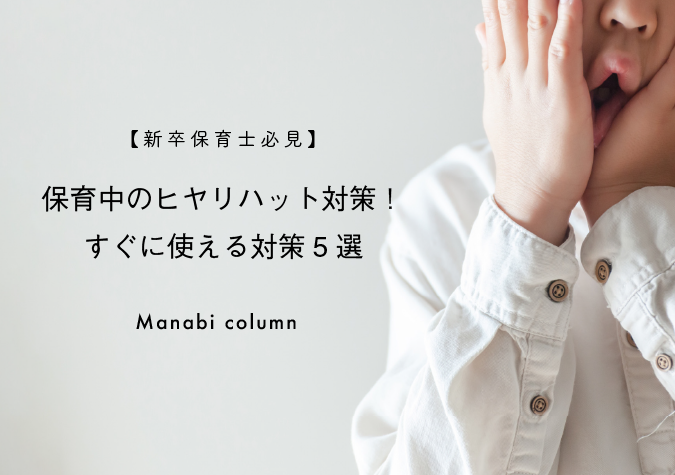
保育の中で危ない!とヒヤっとする経験ありませんか? 子どもに怪我をさせないように、緊張しながらの保育…疲れてしまいますよね。 この記事では、保育中によくあるヒヤリハットや対策について記載していきます。 最後まで読んで、保育に活かしてくださいね。
index
1.ヒヤリハットとは?
2.保育中によくあるヒヤリハット
室内での保育でよくあるヒヤリハット
屋外での保育でよくあるヒヤリハット
3.ヒヤリハット対策5選
①保育士同士での情報共有
②常に子どもの人数を把握する
③声に出して指差し確認
④環境整備
⑤過去のヒヤリハットを把握
4.保育中のヒヤリハット対策まとめ
1.ヒヤリハットとは?
一般的にヒヤリハットとは以下のように定義されています。
“ヒヤリハットとは、危ないことが起こったが、幸い災害には至らなかった事象のことです。”
保育におけるヒヤリハットとは転倒や噛みつき等大きな事故には至らないが、危険を感じた場面のことです。
大きな事故の手前となるヒヤリハットを共有することで、大きな事故防止に繋がります。
2.保育中によくあるヒヤリハット
保育中によくあるヒヤリハットを
①室内での保育でよくあるヒヤリハット
②屋外での保育でよくあるヒヤリハット
②屋外での保育でよくあるヒヤリハット
の2つに分けて紹介していきますね。
室内での保育でよくあるヒヤリハット
室内での保育中によくあるヒヤリハットとしては以下5点があります。
・誤飲
・転倒
・噛みつき
・指挟み
・閉じ込め
・転倒
・噛みつき
・指挟み
・閉じ込め
室内ではおもちゃや小さな部品等の小さなものの誤飲の危険があります。
年齢に適したおもちゃの大きさへの配慮が必要です。
また、保育士の持ち物が床に落ちてしまう可能性もあります。
床や子どもの手の届く場所に危険がないか常に意識を向けましょう。
また、室内にはおもちゃ棚や机があるので、転倒した先の棚にぶつかり怪我をすることもありますね。
子ども目線で危険はないか、環境設定をする必要があります。
マットのめくれや床の濡れ等も転倒のきっかけになるので気をつけましょう。
子ども同士のやりとりの中で噛みつきやひっかき等が起きることもあります。
噛みつきやすい子や手が出てしまう子は保育士同士で共有し、常に保育士が側に付くようにする等の配慮が必要です。
室内ドアでの指挟みや閉じ込めもヒヤリハットでよく見られる事象です。
ドアの開け閉めの際には周囲の子どもへの配慮、人数確認をして、事故を防止していきましょう。
参照:消費庁「保育園等における窒息や誤飲に関する事故防止対策の重要性 」
屋外での保育でよくあるヒヤリハット
屋外での保育中によくあるヒヤリハットとして以下3点があります。
・遊具からの転落
・飛び出し
・置き去り
・飛び出し
・置き去り
屋外では滑り台やブランコ等落下の遊具からの転落の危険があります。
室内遊具と比べて大きく体を動かせる遊具があり、子どもたちの気持ちが高まり、興奮気味になることが多いです。
より注意して見守ることが重要ですよ。
場所にもよりますが、室内での保育と比べて開かれた空間であることが多いので、とくに道路の近くでは飛び出しにも注意が必要です。
公園から園に帰る際の人数確認を怠り、置き去りにしてしまうケースもあります。
屋外では室内と異なる危険がたくさんあるため、散歩コースや公園の危険箇所をリストアップして、共有しておくことがおすすめですよ。

3.ヒヤリハット対策5選
室内、屋外さまざまなヒヤリハットを挙げてきました。
ここではヒヤリハット対策を以下5つ紹介していきます。
①保育士同士での情報共有
②常に子どもの人数を把握
③声に出して指差し確認
④環境整備
⑤過去のヒヤリハットを把握
②常に子どもの人数を把握
③声に出して指差し確認
④環境整備
⑤過去のヒヤリハットを把握
一つずつ詳しく解説していきますね。
①保育士同士での情報共有
一緒に保育をする保育士同士で、危険なことや気になることはこまめに確認し合いましょう。
情報共有をする中で、自分では気づかなかった危険な部分に気づくこともできますよ。
また、保育中「私はここ見てます!」等声をかけ合うこともヒヤリハット対策に有効です。
誰かが見てくれているだろう…との思い込みをなくし、保育士の目を子ども全体に向けられますよ。
何より保育士同士が細些なことでも声をかけ合える関係性であることが事故防止に一番大切な要因だと思います。
大きな事故防止に重要なのは、ヒヤリハットをこまめに共有することです。
保育士同士の関係作りにも目を向けてほしいです。

②常に子どもの人数を把握する
登園人数だけでなく、遅く登園してきた子、早退する子等イレギュラーが起きることもあり、1日の中でもクラスの人数は変わります。
そのため、場面が変わるごとに人数確認をする癖をつけることが大切です。
人数確認においても「誰かが数えているだろう」は禁物です。
人数確認を徹底することで、閉じ込めや置き去り予防に繋がりますよ。
また、複数の保育士で人数確認するとより安心です。
一緒に組む保育士同士で人数確認を意識し合い、活動場所が変わる移動の際などは「◯人確認しました」等と声をかけ合いましょう。
声に出すことで、そのときの子どもの人数をより意識できますよ。

③声に出して指差し確認
子どもの人数確認をするときや置き去り確認をする際は、声に出しながら指差しで確認をしましょう。
目視だけでなく、指差しをすることで自分の意識を向けられ、より正確に確認できます。
幼児では、「誰もいない?」「ドア閉めるよ」と子どもに話しかけるように声を出すことも効果的。
一緒に組む保育士に「トイレ確認してきます」「確認しました」と声をかけることで、確認漏れがなくなりますよ。

④環境整備
おもちゃの破損や棚、机等の角が尖っていないか、怪我に繋がらないかを定期的に確認しましょう。
「時間がある時に確認しよう」だと優先順位が低くなってしまい、なかなか環境整備ができません。
“金曜日の午睡時間”等、具体的に環境整備の時間を設けるのがおすすめです。
公園等屋外での活動場所では、遊び始める前に危険がないかを確認しましょう。
ゴミやタバコの吸い殻等は口に入れてしまう危険もあるため、落ちていたら撤去します。
気温が高くなって来ると遊具の表面も熱くなってしまうので、滑り台や鉄棒等は必ず手で触れて温度を確認しましょう。
遊具が問題なく使用できるかも必ず確認するべきポイントです。

⑤過去のヒヤリハットを把握
園内で過去に起きたヒヤリハットは一つにまとめてあると思います。
園内のどんな場所で危険な場面があったのかを把握することで、保育の中での気をつけるポイントに気づけます。
園内で起きた過去のヒヤリハットは確認しておきましょう!

4.保育中のヒヤリハット対策まとめ
ここまでヒヤリハット対策を5つ挙げてきました。
どの対策も自分の意識次第で明日からすぐに取り入れられるものだと思います。
どうしてもヒヤリハット=悪いことと捉えてしまう人もいますが、ヒヤリハットを積極的に出していくことで大きな事故防止になります。
私は以前ヒヤリハットの対応が異なる2つの園に勤めていました。
1つ目の園はヒヤリハットを起こした職員を責める雰囲気の園。
ヒヤリハットが起きると報告書作成までに、園長やクラス職員での話し合いで時間がかかっていました。
ヒヤリハット報告書作成のために、他の事務作業が進まなくなってしまうので、ヒヤリハットを隠蔽するリーダー層もいるくらいでした。
その園では、ヒヤリハットの共有が少なく、園児が受診する程の怪我が何件も起きていましたよ。
2つ目の園はヒヤリハットをすぐに出し合う園。
ヒヤリハットが起きたら、その日のうちに全職員に共有。
次の日の保育から全職員が危険な部分に気をつけて保育ができ、大きな事故もあまり起こりませんでした。
私は1つ目の園でヒヤリハットは悪いこと、起こしちゃいけないものと思い込んでいたので2つ目の園に行き衝撃を受けました。
ですが、ヒヤリハットの目的は大きな事故を防ぐことです。
積極的にヒヤリハットを共有して保育中の事故を防いでいきましょう!
執筆者:ほいコレ 編集部