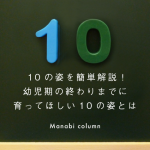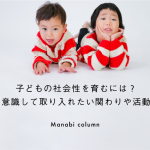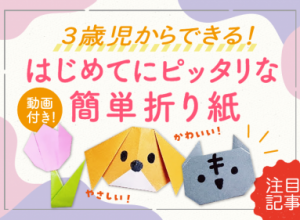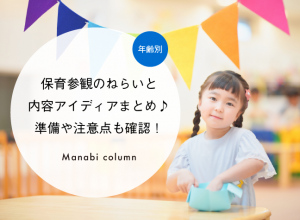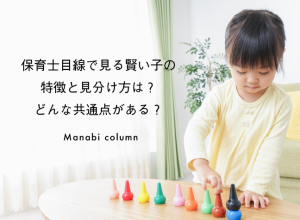非認知能力を育てる保育とは?保育者が意識するポイントと保育実践例
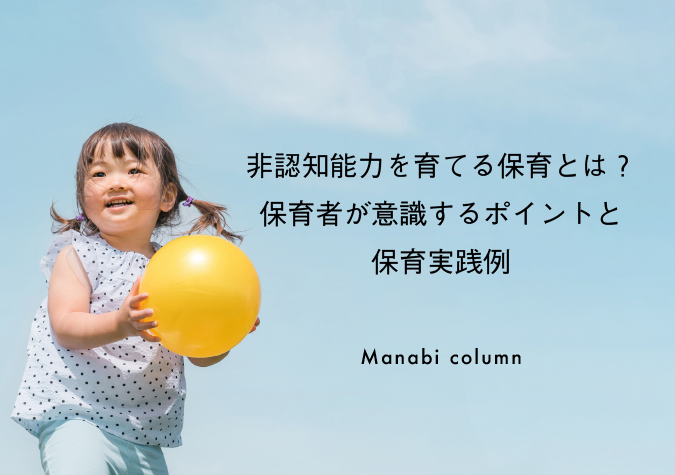
「 非認知能力 を育む保育」を徹底解説!子どもたちの主体性や協調性を伸ばす保育のポイントや遊びの実践例を紹介。未来の保育者が知っておきたい重要なヒントが満載!「なんだか難しそう。」と思っていませんか?そんなあなたに読んでもらいたい情報です。
index
1. 非認知能力 を育む保育とは?
2.保育所保育指針が大切にする 非認知能力 とは?
3. 非認知能力 を育むために保育者が意識する5つのポイント
4. 非認知能力 を育む遊びの保育実践例8つ
①水遊び(感覚と協調性を育てる遊び)
②砂場遊び(創造力と協力性を育てる遊び)
③積み木遊び(空間認識と問題解決力を育てる遊び)
④自然観察(感受性と探究心を育てる遊び)
⑤工作・製作(創造力と集中力を育てる遊び)
⑥リズム遊び(身体表現と自己調整力を育てる遊び)
⑦ごっこ遊び・表現遊び(想像力と社会性を育てる遊び)
⑧絵本の読み聞かせ(共感力と言語感覚を育てる時間)
5. 非認知能力 を育む保育を実践しよう
子どもたちが夢中になって遊んでいるとき、大切な力が育まれていることを知っていますか?
遊びの中で子どもたちはお友だちと協力したり、感情をコントロールしたり、困難に挑戦したりと、非認知能力を少しずつ身につけています。
遊びの中で子どもたちはお友だちと協力したり、感情をコントロールしたり、困難に挑戦したりと、非認知能力を少しずつ身につけています。
そんな子どもたちをサポートする保育者にはどんな役割が求められるのでしょうか?
非認知能力を育む保育は、特別に難しいことをするわけではありません。この記事では、 非認知能力 を育む遊びや保育者として意識したいポイントをお伝えします。
非認知能力を育む保育は、特別に難しいことをするわけではありません。この記事では、 非認知能力 を育む遊びや保育者として意識したいポイントをお伝えします。
未来の保育者として、子どもたちの成長を見守るヒントを一緒に学びましょう!
1. 非認知能力 を育む保育とは?
「 非認知能力 を育む保育」とは、子どもの主体性を重視し、遊びや日常生活を通じて様々な能力を育む保育方法です。
非認知能力とは、数値化が難しい心の動きや社会情動的スキルを指し、認知能力とは異なる能力です。
具体的には、忍耐力、自己抑制、社交性、思いやり、自尊心などになります。
この能力は特に幼児期に大きく発達し、人格形成や将来の成功に影響を与えるとされています。
具体的には、忍耐力、自己抑制、社交性、思いやり、自尊心などになります。
この能力は特に幼児期に大きく発達し、人格形成や将来の成功に影響を与えるとされています。
2.保育所保育指針が大切にする 非認知能力 とは?
保育所保育指針では、 非認知能力 を育む内容が多くあります。
では、なぜ幼児期に 非認知能力 を育てるのでしょうか?
幼児期は、子どもの脳が急速に発達する重要な時期だからです。
この時期の経験や環境は、 非認知能力 の形成に大きな影響を与えます。
そして、育まれた 非認知能力 は、これからの人生で重要な役割を果たすことになります。
幼児期に 非認知能力 を育てることは、子どもたちの将来を豊かにするための基盤を築くためなのです。
この時期の経験や環境は、 非認知能力 の形成に大きな影響を与えます。
そして、育まれた 非認知能力 は、これからの人生で重要な役割を果たすことになります。
幼児期に 非認知能力 を育てることは、子どもたちの将来を豊かにするための基盤を築くためなのです。

「保育所保育指針」に出てくる 非認知能力
第1章総則の保育の目標
・人との関わりの中で、自主、自立及び協調の態度を養う
・豊かな感性や表現力を育む
・創造性の芽生えを培う
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
第1章の4.(2)で示される10の姿
・自立心
・協同性
・道徳性・規範意識の芽生え
・思考力の芽生え
各年齢区分の保育内容
1歳以上3歳未満児、3歳以上児の保育内容の中で、 非認知能力 に関連する要素が多く含まれています。
特に「人間関係」「言葉」「表現」の領域で顕著です。
保育の方法における重視点
子どもの主体性、自発性、探索意欲を尊重し、環境を通して行う保育を重視しています。
これらは 非認知能力 の育成につながる方法です。
3. 非認知能力 を育むために保育者が意識する5つのポイント

保育者として意識すべきポイントは、保育者が一方的に指示するような形ではなく、こどもが主体的に行動できるような援助をすることです。
子どもの興味や成長に合わせたサポートが大切です。
子どもの興味や成長に合わせたサポートが大切です。
1.子どもが主体的に行動できる環境を整えて見守る
遊び場や生活環境を整えることが必要です。
保育は準備がとても大切なのです。
子どもたちが興味をもって安全に遊べるような環境を準備しておきましょう。
保育は準備がとても大切なのです。
子どもたちが興味をもって安全に遊べるような環境を準備しておきましょう。
2.友だちとかかわる機会をつくる
みんなで協力することを学びます。
感情を言葉で相手に伝えるコミュニケーショントラブルが起きた時には、どうしたらいいのかを自分たちで考えられるように導くことが大切です。
感情を言葉で相手に伝えるコミュニケーショントラブルが起きた時には、どうしたらいいのかを自分たちで考えられるように導くことが大切です。
3.成功体験を積極的に認め自己肯定感を高める
時間をかけて成長を見守る姿勢が大切です。
成功体験を認めて、子どもの自己肯定感を高めましょう。
成功体験を認めて、子どもの自己肯定感を高めましょう。
4.挑戦できる環境作り
自分の失敗を受け入れられる環境で、子どもは安心感を感じられます。
失敗しても大丈夫だと思うことで、新しいことに挑戦しようと思う気持ちが芽生えます。
失敗しても大丈夫だと思うことで、新しいことに挑戦しようと思う気持ちが芽生えます。
5.子どもの選択を尊重する
保育士の一方的な指示にならないように、子どもの思いにも寄り添いましょう。
こどもの選択を尊重することが大切です。
こどもの選択を尊重することが大切です。
4. 非認知能力 を育む遊びの保育実践例8つ
非認知能力を鍛える遊びは、子どもの興味・関心によってたくさんの種類があります。
クラス・子どもの実態に合わせて、どのような遊びを取り入れていけばいいのかを考えることが重要です。
どの遊びも保育者が一方的に指示するような形ではなく、こどもが主体的に遊べるような援助をすることを意識しましょう。
クラス・子どもの実態に合わせて、どのような遊びを取り入れていけばいいのかを考えることが重要です。
どの遊びも保育者が一方的に指示するような形ではなく、こどもが主体的に遊べるような援助をすることを意識しましょう。
1.水遊び(感覚と協調性を育てる遊び)
保育実践例
ビニルプールで遊ぶ(0.1歳児)
ねらい:友だちと一緒に水の感触を楽しみながら遊ぶ
水の冷たさや感触を通して、感覚が刺激されます。
友だちとふれあいながら遊ぶことで、コミュニケーション能力も育まれます。
水遊びは安全面の配慮が必要です。
夏場の水遊び・どろんこ遊びはもちろん、他の季節では泥団子作りもおすすめです。
友だちとふれあいながら遊ぶことで、コミュニケーション能力も育まれます。
水遊びは安全面の配慮が必要です。
夏場の水遊び・どろんこ遊びはもちろん、他の季節では泥団子作りもおすすめです。
2.砂場遊び(創造力と協力性を育てる遊び)
砂場でみんなでまちを作る(5歳児)
ねらい:友だちと協力しながら、イメージを膨らませて砂場遊びをする
ねらい:友だちと協力しながら、イメージを膨らませて砂場遊びをする
保育実践例
砂で様々なイメージをもちながら形を作りアイデアを実現することで創造力が磨かれます。
みんなで一緒に遊ぶ中で、道具の貸し借りをしたり、トラブルを解決したり、コミュニケーション能力が育まれます。
みんなで一緒に遊ぶ中で、道具の貸し借りをしたり、トラブルを解決したり、コミュニケーション能力が育まれます。
3.積み木遊び(空間認識と問題解決力を育てる遊び)
コーナー遊び[積み木・パズル・ドミノ・お絵描きなど](4歳児)
ねらい:好きな遊びをみつけ、試行錯誤しながら楽しむ
保育実践例
自分で好きな遊びを選ぶことも大切です。
パズルを考えながら遊ぶことで空間認識や問題解決力が育まれます。
創造力や集中力も養えます。
パズルを考えながら遊ぶことで空間認識や問題解決力が育まれます。
創造力や集中力も養えます。
4.自然観察(感受性と探究心を育てる遊び)
保育実践例
秋をみつけに散歩へいく(3歳児)
ねらい:季節の移り変わりを知り、自然物に興味をもつ
ねらい:季節の移り変わりを知り、自然物に興味をもつ
季節の移り変わりに気が付くような声かけをして散歩しましょう。
子どもが自分で発見できると、嬉しそうに教えてくれます。
興味・関心に繋がり、探究心が育ちます。
子どもが自分で発見できると、嬉しそうに教えてくれます。
興味・関心に繋がり、探究心が育ちます。
5.工作・製作(創造力と集中力を育てる遊び)
保育実践例
廃材製作(5歳児)
ねらい:イメージを膨らませながら製作を楽しむ
ねらい:イメージを膨らませながら製作を楽しむ
自分でイメージをもち、「この廃材はどこの部分に使おうかな?」と考える課程が大切です。
試行錯誤しながら作り上げていき、創造力や集中力を育てます。
試行錯誤しながら作り上げていき、創造力や集中力を育てます。
6.リズム遊び(身体表現と自己調整力を育てる遊び)
保育実践例
リトミック(2歳児)
ねらい:ピアノの音に合わせて、身体をうごかす
ねらい:ピアノの音に合わせて、身体をうごかす
ピアノの音に合わせて、「歩く・ストップ」など、簡単な動きからスタートしましょう。
いろいろな音にのせて身体を動かせるようになってくると、身体表現が楽しくなってきます。
自己調整力にもつながっていきます。
いろいろな音にのせて身体を動かせるようになってくると、身体表現が楽しくなってきます。
自己調整力にもつながっていきます。
7.ごっこ遊び・表現遊び(想像力と社会性を育てる遊び)
保育実践例
劇ごっこ[1場面をみんなで意見を出しながら進める](4歳児)
ねらい:登場人物の気持ちや表情などを考え、表現する
ねらい:登場人物の気持ちや表情などを考え、表現する
ごっこ遊びは、想像力やコミュニケーション能力、社会性を育むのに効果的です。
場面ごとの登場人物の気持ちを考えながら取り組むことで、想像力や、協調性、問題解決能力も育むことにつながります。
場面ごとの登場人物の気持ちを考えながら取り組むことで、想像力や、協調性、問題解決能力も育むことにつながります。
8.絵本の読み聞かせ(共感力と言語感覚を育てる時間)
保育実践例
絵本の読み聞かせ(3歳児)
ねらい:絵本の世界を友だちと共有しながら楽しむ。
ねらい:絵本の世界を友だちと共有しながら楽しむ。
子どもたちは絵本が大好きです。
絵本の物語の世界を楽しみながら、共感力や言語感覚も育まれていきます。
絵本の物語の世界を楽しみながら、共感力や言語感覚も育まれていきます。
5. 非認知能力 を育む保育を実践しよう
「 非認知能力 を育む保育」とは、子どもの主体性を重視し、遊びや日常生活を通じて様々な能力を育む保育方法です。忍耐力、自己抑制、社交性、思いやり、自尊心が育まれるように援助していきます。
保育士の役割としての5つのポイント
・子どもが主体的に行動できるよう、環境を整えて見守る
・友達とかかわる機会をつくる
・成功体験を積極的に認め、自己肯定感を高める
・失敗も受け入れられる挑戦できる環境作り
・保育士が一方的に指示することのないよう、子どもの選択を尊重する
子どもたちの成長を見守りながら、一緒に成長していきましょう!
執筆者:まこ 先生(保育教諭1)