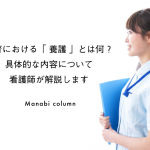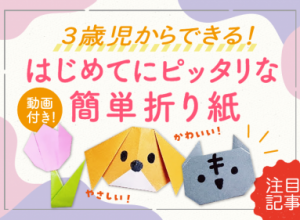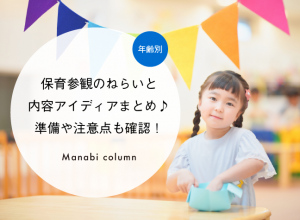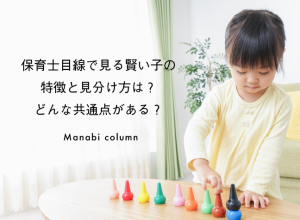【保育】2歳児の 養護 のねらいは?看護がかんたん解説します

保育には 養護 の視点がとても大切。保育園では年齢や月齢に応じて、子ども達との関わり方が変わってきます。今回は2歳児の 養護 のねらいと具体的な内容を、看護師の私から保育学生さんに向けてお伝えします。実習で役に立てたら嬉しいです。
index
1. 2歳児の 養護 のねらい
2. 保育に役立つ!2歳児の 養護 の内容をご紹介
・お友達との関わりをサポートする
・自分で着替えができるように見守る
・手洗い・うがいを習慣化できるようにサポート
・トイレで排泄することを見守る
3.子どもを見守ることが 養護 につながる
1. 2歳児の 養護 のねらい
実習でどのように子ども達と関わろうか、何をして遊ぼうか悩んでいる保育学生さんは多いのではないでしょうか。
今回は、2歳児の 養護 の内容についてご紹介します。
2歳児は、言語能力や運動能力が発達し、自分でやりたい!という気持ちが増えていきます。そのため、いわゆる「イヤイヤ期」が来るのもこの時期。
まずは、2歳児の発達についておさえておきましょう!
2歳児の発達の特徴
・二語文を話すようになり、言葉が盛んになる
・自分本位の行動が目立ち、思い通りにいかないと怒ったり、頑固になったりする
・手づかみをすることが減り、スプーンやフォークを使って食事をするようになる
・身の回りのことを自分でやりたがる
・トイレに行きたいことを言葉や仕草で伝える、または保育士が促すことで便器の排泄をする
・一緒に遊んでいるお友達の名前を呼ぶ
1歳児よりもさらに自我が芽生え、思い通りにいかないことがあると激しく泣いたり、怒ったりすることがあります。
保育学生さんは、このような子どもの姿を見て「どうしよう…」と焦ることがあると思いますが、このような子どもの行動は成長過程でとても大切なこと。
子どもの気持ちを代弁し、やさしく見守ることで信頼関係が生まれてきます。
2. 保育に役立つ!2歳児の 養護 の内容をご紹介
つぎに、具体的に2歳児の 養護 の内容についてお伝えします。
ぜひ、保育実習の参考にしてくださいね♪
【お友達との関わりをサポートする】
1歳までは一人遊びや、保育士さんと1対1でのかかわりが多いですが、2歳になると徐々に、お友達と遊ぶようになってきます。
お友達と遊ぶのはとても楽しいですが、時にはケンカをすることも…
2歳児はまだ言葉で気持ちを伝えることが難しいので、保育士さんが子ども達の言葉を代弁してあげる必要があります。
例えば、おもちゃの取り合いになってしまった場合。
「おもちゃは順番で使おう」「おもちゃを引っ張ると壊れちゃうからやめようね」とルールを分かりやすい言葉で伝えましょう。
もし癇癪をおこしてしまっている子どもがいたら、静かな場所で背中をさするなどして、気持ちを落ち着かせてから「おもちゃで遊びたかったね」と代弁してあげましょう。
【自分で着替えができるように見守る】
2歳になると、身の回りのことを自分でやりたいと強く思うようになります。
着替えをしている途中に、保育士さんが手伝うことを嫌がる子どももいます。
例えば、着替えている途中に前と後ろを逆に着ようとしている子どもがいても、途中で止めずに最後まで見守りましょう。
保育士さんは、まず自分で最後まで着替えられたことをしっかりと褒めてあげることが大切です。
そのあとに、「洋服の前と後ろが反対になっちゃたから、直したらもっとかっこいいよ!」と声掛けをしましょう。
子ども達に、自分でできた!という自信をつけてあげられるような関わりをしていきましょうね。
【手洗い・うがいを習慣化できるようにサポート】
保育園は集団生活をする場所。一年を通して、感染症対策はとても大事になります。
子ども自身が健康でいるためにはどうしたら良いかを考えられるようにサポートしていきましょう。
「お外遊びをしたあとは手やお口にバイキンさんがいるから、ガラガラぺをしてバイキンさんをやっつけよう!」「ご飯を食べる前に、手をキレイにしてバイキンさんバイバイしよう!」と声掛けをして、手洗い・うがいの習慣化を促していきましょう。
保育士さんは、子どもを見守り、上手にできない子どもにはさりげなく手を差し伸べてあげましょうね。
【トイレで排泄することを見守る】
1歳児と比べて、2歳児は尿意や便意を言葉で伝えられるようになります。
保育中にトイレでの排泄が成功することが増えてくると思います。
しかし、トイレトレーニングの進み具合は個人差があるので、保育士さんは一人ひとりの進み具合を把握しましょう。
なかには、トイレに行きたいことを伝えることが難しい子どももいるので、モジモジしていたり落ち着きがない時は、保育士さんから「トイレに行ってみようか」と声掛けをしてあげましょう。
失敗してしまっても叱らずに「今度は少し早めにトイレに座ってみよう」と伝えてみましょう。
3. 子どもを見守ることが 養護 につながる
保育学生さんに向けて、2歳児の 養護 の内容についてお伝えしました。
1歳と比べて大きく変化することは、少しずつお友達同士の関わりが増えることと、自分でやりたいという気持ちが大きくなることだと思います。

いそがしい保育中に、子どもの行動を根気強く見守るのはとても大変なことです。
ですが、できる範囲で子どもの気持ちを尊重してあげてくださいね。
保育学生さんの参考になれば嬉しいです。
執筆者:瀬川知子(看護師)