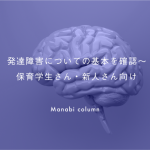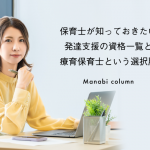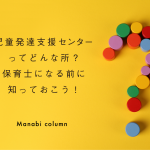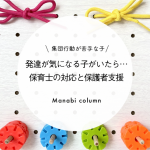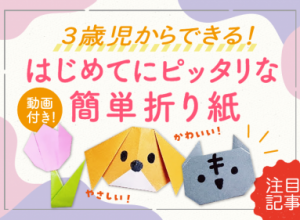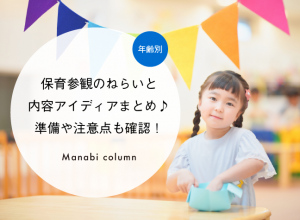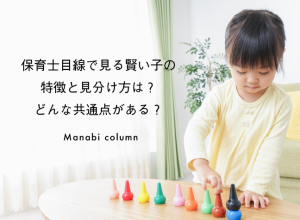保育実習中から役立つ! 発達支援 保育の第一歩(子どもへのかかわり方)
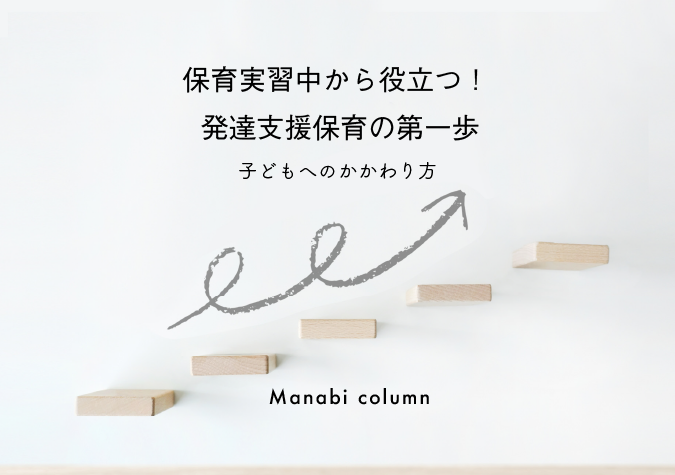
発達支援保育が必要な子どもへの接し方に悩んでいる保育学生さんへ。個性を理解し、適切な支援を行うことの重要性を解説します。発達障害の基礎知識や具体的な子どもへのかかわり方のポイントを学び、一緒にスキルアップを目指しましょう!
index
1. 発達支援 保育とは?
2. 保育学生のうちに知っておきたい発達障害の知識
・よくみられる発達障害の特徴と困りごと
【集団が苦手】
【コミュニケーションが苦手】
【イメージすることが苦手】
【感覚や運動面に特徴がある】
・児童 発達支援 の5領域
3. 発達支援 保育の第一歩(子どもへのかかわり方)
・発達のでこぼこを理解する
・具体的な短い言葉で声をかける
・禁止ではなく肯定的に伝える
・はじめとおわりをはっきりさせる
・安心する場、物を把握しておく
・絵カードを利用する
4. 保育士が知っておきたい 発達支援 の資格や施設
5. 発達支援 保育を実践しよう
保育実習中「この子にはどう接すればいいのだろう?」と悩むことはありませんか?
発達支援が必要な子どもにとって、個性を理解してくれる保育士の存在は大きな支えとなります。
では、発達支援 とは何でしょう?
わかりやすいイメージでお話しすると、視力が低い子には、メガネをかけてあげますよね。
このメガネをかけることが保育士のできる支援です。(※イメージです)
わかりやすいイメージでお話しすると、視力が低い子には、メガネをかけてあげますよね。
このメガネをかけることが保育士のできる支援です。(※イメージです)
子どもの個性である発達のでこぼこ部分を理解して、その苦手な部分を少しでも埋めてあげられるように援助することが必要です。
この記事では、実習中にすぐに取り入れられる 発達支援 の基本(子どもへのかかわり方)や保育学生のうちに知っておきたい発達障害の知識をお伝えします。
一緒に 発達支援 保育の第一歩を学びましょう。
1. 発達支援 保育とは?
発達支援保育とは、障害のある子どもや発達が気になる子どもに対して行われる総合的な支援保育のことです。
子どもの個性や特性を正しく理解して、適切に支援することが目的です。
一人ひとりのニーズに合う支援が適切に行われれば、子どもは自分のペースで成長していきます。
また、 発達支援 を学ぶことで、どのような子どもにも適切に対応できる保育士のスキルが身につきますよ。
一人ひとりのニーズに合う支援が適切に行われれば、子どもは自分のペースで成長していきます。
また、 発達支援 を学ぶことで、どのような子どもにも適切に対応できる保育士のスキルが身につきますよ。
2. 保育学生のうちに知っておきたい発達障害の知識

適切な発達支援保育をおこなうためには、よくみられる発達障害の特徴と困りごとを知ることが大切です。
また、児童 発達支援 の5領域についても学んでおきましょう。
また、児童 発達支援 の5領域についても学んでおきましょう。
よくみられる発達障害の特徴と困りごと
集団が苦手
- 社会的ルールを理解することが難しい(空気を読むことが難しい)
- 大勢の人の輪のなかに入ることが難しい
コミュニケーションが苦手
- 指示の理解が難しい
- 状況把握が難しい
- 意思表示が難しい
イメージすることが苦手
- 夢中になると次の行動へうつれない
- 1つの遊びを続けることが難しい
- はじめてのこと難しい
- 勝敗、1番にこだわる
感覚や運動面に特徴がある
- 音や感触への抵抗
- 周りの刺激に気が散る
- からだの姿勢やバランスを保つことが難しい
- 手先が不器用で操作が難しい
関連記事 発達障害のタイプや診断名についてはこちら
児童 発達支援 の5領域
こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズ等の把握に当たっては、本人支援の5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要である。
1. 健康・生活
目標:健康管理、生活リズムの確立、基本的生活スキルの獲得
内容:清潔保持、食事、衣類の着脱、排泄、規則正しい生活リズムの形成
内容:清潔保持、食事、衣類の着脱、排泄、規則正しい生活リズムの形成
2. 運動・感覚
目標:姿勢と運動・動作の向上、感覚の総合的な活用
内容:姿勢保持、身体の動かし方、移動能力の向上、五感の活用
内容:姿勢保持、身体の動かし方、移動能力の向上、五感の活用
3. 認知・行動
目標:認知の発達と適切な行動の習得
内容:情報の認知と処理、状況判断、ルールの理解、数量・大小・重さ・色の理解
内容:情報の認知と処理、状況判断、ルールの理解、数量・大小・重さ・色の理解
4. 言語・コミュニケーション
目標:言語の形成と活用、コミュニケーション能力の向上
内容:言葉の習得と表現、相手の言葉の理解、コミュニケーション手段の選択と活用
内容:言葉の習得と表現、相手の言葉の理解、コミュニケーション手段の選択と活用
5. 人間関係・社会性
目標:他者との関わりの形成、自己理解と行動の調整
内容:仲間づくり、集団への参加、自己の理解と行動の調整
内容:仲間づくり、集団への参加、自己の理解と行動の調整
5領域を包括的に支援することで子どもたちの全体的な成長を促します。
3. 発達支援 保育の第一歩(子どもへのかかわり方)

子どもの個性・特徴を理解しようと心がけながら、向き合うことが大切です。
ここでは、かかわり方のポイントを紹介します。
子どもによっても違うので、これが正解というわけではありません。
試行錯誤しながら、かかわりを深めていきましょう。
ここでは、かかわり方のポイントを紹介します。
子どもによっても違うので、これが正解というわけではありません。
試行錯誤しながら、かかわりを深めていきましょう。
発達のでこぼこを理解する
支援の必要な子どもは、得意なことと苦手なことの差(でこぼこ)がある
でこぼこを保育士が理解していないと、子どもは困ってしまうのです。
その子のでこぼこを理解し、少しでも困りごとがなくなるように援助することが大切です。
その子のでこぼこを理解し、少しでも困りごとがなくなるように援助することが大切です。
具体的な短い言葉で声をかける
短く、タイミングをみて、具体的に伝える
長い声かけは何が大切なことなのかわからなくなってしまいます。
子どもの気持ちがこちらに向いた時に、大声ではなく語りかけるように伝える方がよいでしょう。
子どもの気持ちがこちらに向いた時に、大声ではなく語りかけるように伝える方がよいでしょう。
禁止ではなく肯定的に伝える
「だめ」ではなく、「〇〇しよう」と伝えることが大切
状況把握が難しい子どもには、禁止の言葉は理由がわからなかったり、子どもを苦しめたりすることもあります。
一度に1つのメッセージを伝え、できたことは褒めるようにしましょう。
状況把握が難しい子どもには、禁止の言葉は理由がわからなかったり、子どもを苦しめたりすることもあります。
一度に1つのメッセージを伝え、できたことは褒めるようにしましょう。
はじめとおわりをはっきりさせる
活動のはじめとおわりをはっきりすると安心して活動に参加できる
「いつまで」「どこまで」をはっきりわかるように知らせることを心がけましょう。
視覚的に知らせてあげることも効果的です。
「いつまで」「どこまで」をはっきりわかるように知らせることを心がけましょう。
視覚的に知らせてあげることも効果的です。
安心する場、物を把握しておく
不安になった時の安心材料を把握しておく
困り事が多く、情報処理できなくなってしまうようなとき、パニックになってしまう子もいます。
安全で一人になれる空間・持っておくと落ち着くタオルなど、その子の安心材料を知っておくことが必要です。
困り事が多く、情報処理できなくなってしまうようなとき、パニックになってしまう子もいます。
安全で一人になれる空間・持っておくと落ち着くタオルなど、その子の安心材料を知っておくことが必要です。
絵カードを利用する
何かを指示する時は絵カードや写真を利用すると理解しやすい
きいたことを理解するより、目に見えるものを理解しやすい特徴があります。
子どもの正面から向き合った状態で伝えることも大切です。
きいたことを理解するより、目に見えるものを理解しやすい特徴があります。
子どもの正面から向き合った状態で伝えることも大切です。
4. 保育士が知っておきたい 発達支援 の資格や施設
発達支援 に携わる場は、保育園や幼稚園だけではなく、数種類あります。
関連施設や資格についても知っておくと、知識が深まりますよ。
発達支援 保育に関わる資格
・保育士、幼稚園教諭
・児童発達支援士
・児童発達支援管理責任者
・理学療法士(PT)
・作業療法士(OT)
・言語聴覚士(ST)
・臨床心理士
・公認心理師
・発達障害児支援士
・子ども 発達障害支援 アドバイザー
・保育士、幼稚園教諭
・児童発達支援士
・児童発達支援管理責任者
・理学療法士(PT)
・作業療法士(OT)
・言語聴覚士(ST)
・臨床心理士
・公認心理師
・発達障害児支援士
・子ども 発達障害支援 アドバイザー
施設や取り組み
・保育園、幼稚園、こども園など
・放課後デイサービス
・児童 発達支援 センター
・療育施設
・ことばの教室
・発達相談
・保育所等訪問支援
・保育園、幼稚園、こども園など
・放課後デイサービス
・児童 発達支援 センター
・療育施設
・ことばの教室
・発達相談
・保育所等訪問支援
※併行通園も取り入れられています。
併行通園とは、通常の保育園や幼稚園に通いながら、児童発達支援センターなどの専門施設で療育を受ける方法です。
子どもが集団生活を経験しながら、個別の発達ニーズに応じた支援を受けられます。
併行通園とは、通常の保育園や幼稚園に通いながら、児童発達支援センターなどの専門施設で療育を受ける方法です。
子どもが集団生活を経験しながら、個別の発達ニーズに応じた支援を受けられます。
関連記事 発達支援の資格一覧はこちら
5. 発達支援 保育を実践しよう
発達支援保育とは、障害のある子どもや発達が気になる子どもに対して行われる総合的な支援保育のことです。
どのような子どもでも、得意・不得意のでこぼこがあります。
子どもの個性・特性を理解し、試行錯誤しながら、子どもと共に成長していきましょう。
保育実習のクラスの気になる子どもへ、 発達支援 の第一歩(子どもへのかかわり方)を早速実践してみてくださいね。
保育学生のうちに、発達支援保育について知識を深め、適切な支援のできる保育士を目指しましょう。
執筆者:まこ 先生(保育教諭1)