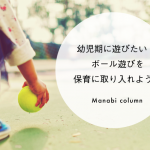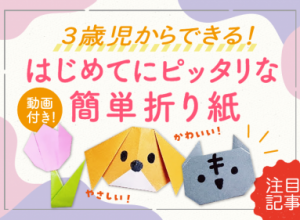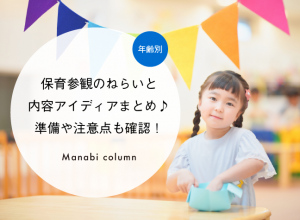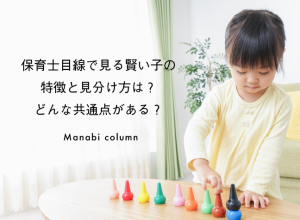【保育】みんなで サッカー がしたい!ボール蹴り遊びから入る サッカー の始め方 保育・サッカー
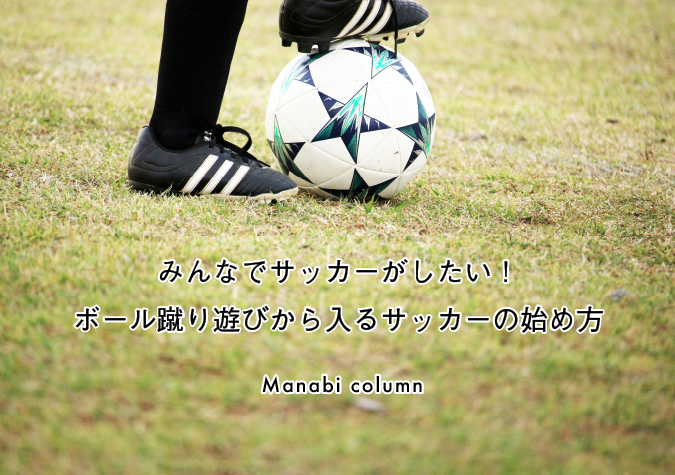
ボール遊びって楽しいですよね!幼稚園や保育園では、ボール遊びの延長で サッカー を取り入れる園が多いです。 サッカー には、体力だけでなく体幹やバランス感覚も高める効果があります。まずは楽しんでボールに慣れるところから始めましょう!先生も一緒に サッカー を楽しんでくださいね。
1. 大人気!保育に サッカー を取り入れよう
幼少期に サッカー を取り入れる園は多いです。
幼稚園の課外教室や習い事などでもよく聞きますよね。
今日は保育に取り入れたい サッカー の遊び方についてご紹介します。
どうして幼少期に サッカー が人気なのでしょう?
まず、ボール蹴り遊びは、蹴ることによって下半身の発達を促すことができます。
蹴る動作は、蹴る瞬間片足立ちになって、地面から離れている足を思いっきり振る動作となっています。この動作は日常生活ではなかなかしないので、かなり体幹の基礎が育まれます。
また、ボールがどこにあるのか、どこに足を置けばいいのか、どの瞬間ならボールに当たるのかを考えることで、身体操作と動体視力を連動させる力が発達します。
簡単に言えば、見てから身体を動かす力とでも言うのでしょうか。
車の運転で例えるのであれば、危ない!と思ってからブレーキをかける早さが、連動させる力だと私は考えます。
また、蹴る力のコントロールする能力、転がっているボールを止める能力など、力がついてくれば、そのような細かい動作もできるようになってきます。
実体験エピソード
私の持っていたクラスにTくんという子がいたのですが、Tくんにはお兄ちゃんが2人いて、どちらとも サッカー をしていたそうです。Tくんもその影響で サッカー をしていました。
外遊びの時に一緒に サッカー をしたのですが、びっくりするぐらい上手くて、吸い付くようなドリブルをしていました。
年少さんだったのですが、お兄ちゃんの サッカー を見て影響を受けたのかなと思うと、環境はとても大事だなと思いました。
ですので、ボール遊びの延長で サッカー はいっぱい経験をさせてあげてくださいね!
2. ボール蹴り遊びから始めよう
サッカー を始めるための身体作りの流れをご紹介します。
①ボールと仲良くなろう
年少~年中さんは、 ボールになれていないので、そこから始めます。
ボールをなげてキャッチすると繰り返し遊びます。
また、座った状態で、ボールをコロコロ自分の周りを転がしてストップさせます。
どこでストップさせるか楽しんで遊んでくださいね。
ボールの硬さや大きさに慣れていくステップです。
②鬼ごっこをしよう
サッカー はとにかく走ります。
鬼ごっこをして、走ることに慣れましょう。
こおり鬼や、安全地帯のある鬼ごっこもいいですね!
③ゴールに向かってシュートをしてみよう!
シュートが決まれば点数が入り、有利になるということは、年少さんも知っている子も多いはず。
そうです!ゴールを決めれば、テンションが上がるものなのです!
まずは一人ひとりシュートをしていきましょう。
自分がシュートを打ったら、ゴールに入ったボールを拾って後ろに並ぶ。
これを繰り返すだけでも楽しい運動になりますよ。
④ドリブルの練習をする
ドリブルは サッカー の基本の動きになります。
力いっぱい蹴るのではなく、加減をしながら蹴って、少しずつ進んでいく練習をしていきます。
線から線へドリブルして進む。
ドリブルして進み、先生の笛の合図でピタッと止める⇒進む。
アレンジして楽しい練習をしてみましょう。
ポイント!
ドリブルは、力加減や足の使い方に練習が必要です。
まだ幼少期は難しいので、個人の発達に合わせて遊んでください。
蹴ろうとしたのに誤ってボールの上に乗っかってしまうと、ひっくり返ってしまって頭を強打することもあります。
遊んでいるとヒートアップしがちですが、「最初はゆっくりでいいんだよ」と落ち着いた言葉がけをしてあげましょう。
3. サッカー でケガをしてしまったら…
最後に、万が一 サッカー をしていてケガをしてしまったときの対処法を覚えておきましょう。
いくらルールを決めて、みんながそれを守っていても、思ったより力が入ってしまったり、目測を誤ってぶつけてしまったりと、予想外のことが起こります。
その時にどう対処するか、また迅速な対応が影響すると思われますので、ぜひ知っておいてくださいね。

たくさんあるので基本的な考えの一部を紹介します。
サッカー のようなボール遊びでケガと言えばすり傷や捻挫、打撲などがあげられます。基本的な考えとしては、「RICE処置」というものがあります。
「RICE処置」とは?
Rest…安静
Icing…冷却
Compression…圧迫・固定
Elevation…拳上
の頭文字をとってRICEです。
簡単に言えば、安静にする→冷やす→テーピングなどで固定する→患部を心臓より高い位置に保つ、を順番でやります。
最後の心臓より上で保つことは難しいと思うので、出来る子にはやらせるくらいで大丈夫だと思います。
詳しくは「RICE処置」で調べるといろいろ出てくるので、参考にしてみてくださいね。
執筆者:りんご先生(保育教諭2)