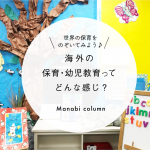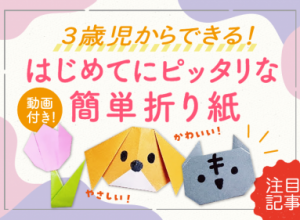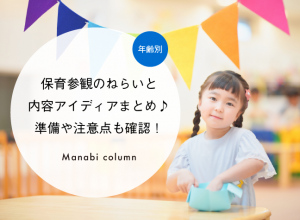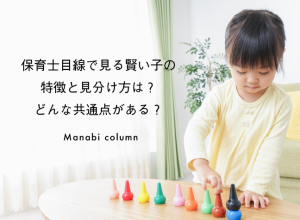子ども主体の保育ってどんな保育?年長児での体験談
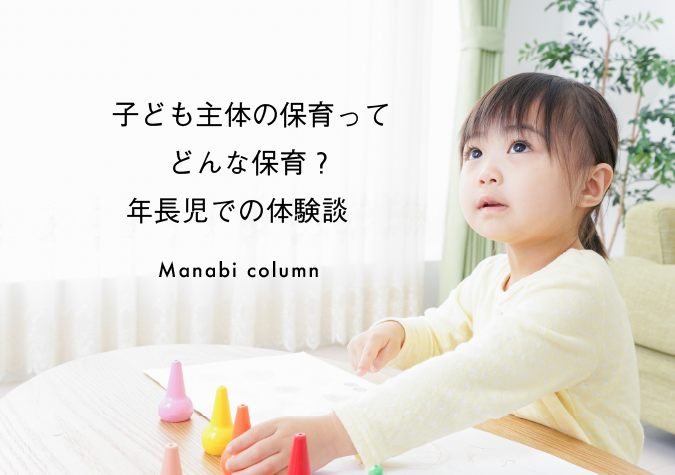
“子ども主体の保育”を実践する保育園は最近増えてきていますよね。 「子ども主体の保育って何?」「どうやって保育を進めているの?」と疑問に思っていませんか? この記事では子ども主体の保育の概要や、実際に年長児での保育実践例を紹介していきます。
index
1.子ども主体の保育って何?
2.子ども主体の保育 体験談3つ
①日々の保育
②行事〜運動会〜
③行事〜お泊まり会〜
3.子ども主体の保育を実践してみて感じたメリット、デメリット
メリット3選
デメリット3選
4.子ども主体の保育の魅力
1. 子ども主体の保育って何?
子ども主体の保育とは、子どもの意思を尊重した子ども中心の保育のことです。
みんなで同じ活動をする一斉保育に対し、自由保育と言われることもあります。
保育所保育指針にも以下のような記載があり、保育の中で子どもの主体性がいかに重視されているかがわかりますよね。
「一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。」
「子どもが自発的・意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること。」

2. 子ども主体の保育 体験談3つ
私自身、子ども主体の保育を実践する保育園での勤務経験があります。
年長児の担任をしていたときの子ども主体の保育の体験談を以下3つに分けて紹介していきますね。
①日々の保育
②行事〜運動会〜
③行事〜お泊まり会〜
②行事〜運動会〜
③行事〜お泊まり会〜
①日々の保育
日中の活動予定は前日の集まりで子どもたちと話し合って決めていました。
園内で遊ぶのか、散歩や公園に行くのか等子どもたちの意見を聞き、保育者は子どもの意見をまとめる役割を担っていました。
もちろん意見が割れてしまうこともあります。
そのようなときには、保育者が「こうしたらどうかな?」と提案をすることもありました。
また、子ども同士で「明日は〇〇公園にして、その次の日に△△公園にしよう!」と提案し合う姿も見られましたよ。
たとえば雨の日には、室内で遊ぶ子と、カッパと長靴で散歩に出かける子の2グループに別れて活動することもありました。
前日に自分たちで次の日の活動を決めることで、次の日の期待感に繋がり、楽しみに登園して来る子が多いなと感じていました。
②行事〜運動会〜
毎年恒例の大きな行事の一つが運動会です。
運動会の時期が近づいて来ると、子どもたちが運動会に興味をもてるように、前年度の運動会の写真を掲示する等のきっかけ作りをします。
私が担任した年長児は、進級したばかりの頃から前年度の年長児が運動会で踊っていたソーラン節への憧れを強く抱いていました。
運動会の時期は先でしたが、子どもたちの興味を大切にし、日々の保育の中でソーラン節を踊る時間を設けていました。
競技内容も子どもたちと話し合って決めていきます。
子どもたちが自分の経験や昨年度までの運動会の思い出、保護者の方たちにどんな姿を見てほしいか等を考えて、意見を出し合います。
“子どもたちのどんな思いがあり、競技が決まったのか”を保護者にしっかりと伝えることも保育者の大きな役割です。
保護者から、競技の内容等について質問や意見をもらうことがあり、話し合いの段階から保護者への情報共有が必要なのだと強く感じていました。

③行事〜お泊まり会〜
運動会と同様、年長児になったらできる!と子どもたちが楽しみにしているのがお泊まり会です。
食事のメニューから活動内容まで、ほとんどすべて子どもたちと話し合いをして決めます。
活動内容はその学年によって流行している遊び等の影響を受けて大きく異なるので、何をするのか保育者として楽しみにしていました。
食事に関しては、子ども一人ひとり好き嫌いがあるため、話し合いが進まないこともあります。
中々意見がまとまらないときに「試食をしてから決めたらいいんじゃない?」と意見が出て、実際にクッキング、試食会をしました。
子ども自身で“何を作りたいのか”を栄養士に伝え、一緒にクッキングの計画を立てました。

子ども主体の保育を行うに当たって、私が大切にしてきたことは、保育者は黒子になることです。
保育者主導で進めてしまえば、何事もスムーズに進むかもしれません。
ですが、子ども自身で考え、意見を伝え合い、実行することで、子ども自身の行事への思い入れが変わってきます。
何より、行事を無事に終えられたときに子ども自身が達成感を得られます。
子ども主体の保育を通して、子どもがもつ無限の可能性を感じていました。
3.子ども主体の保育を実践してみて感じたメリット、デメリット
子ども主体の保育を実践してみて感じたメリット、デメリットは以下3つです。
メリット3選
①子ども自身で考え、行動する力が身に付く
②自分の思いを表現する力が身に付く
③コミュニケーション能力の向上
デメリット3選
①集団行動の経験が少なくなる
②保育者の負担が大きい
③保護者の理解を得るのが難しい
一つずつ解説していきますね。
メリット3選
①子ども自身で考え、行動する力が身に付く
保育者が決めたことではなく、子どものやりたいことを主とするので、子ども自身で考え行動する機会が多くなります。
その結果、保育者の指示待ちをするのではなく、自分で考えて行動する姿が多く見られるなと感じました。
②自分の思いを表現する力が身に付く
保育の中で保育者が子どもの意見を聞く場面が多いので、自分の思いを表現する力が身に付きます。
保育者相手だけでなく、遊びの中で子ども同士でも日常的に思いを表現し合う姿が多く見られました。
話し合いの場面では、発言の多い子、少ない子がいますが、少人数での話し合いの機会を設けることで、発言をする経験を積めていました。
③コミュニケーション能力の向上
話し合いの場面では、回数を重ねるごとに自分の思いを伝えるだけでなく、自分とは異なる意見も受け入れる経験をしていきます。
自分はなぜそう思ったのか理由を伝えたり、友だちの思いを聞いたりとコミュニケーション能力の向上を感じました。

デメリット3選
①集団行動の経験が少なくなる
一斉保育と比較すると、みんなで同じことをする機会が少なくなります。
自分のやりたいことをやっていた保育園時代とは大きく環境が異なるため、小学校入学後にギャップを感じてしまう子もいます。

②保育者の負担が大きい
子どもの思いを 叶えるために、環境を整えたり、準備をしたりとやることが多く、保育者の負担が大きくなります。
一つの活動を決めるだけでも、子どもの意見を聞き、まとめて、準備、実行と多くの労力がかかります。
③保護者の理解を得るのが難しい
子ども主体の保育は、保護者から見ると“放任”のように見られてしまうこともあり、保護者の理解を得るのが難しい場面もあります。
とくに行事では、子どもの成長した姿を見たいと思う保護者が多いです。
行事に至るまでの経緯や子どもの思い、話し合いの様子をドキュメント等で丁寧に伝えていく必要性を強く感じていました。

4.子ども主体の保育の魅力
ここまで、子ども主体の保育の体験談やメリット、デメリットについてまとめてきました
子ども主体の保育は保育者にとって難しさや大変さもあります。
しかし、子ども一人ひとりにライトをあてて、その子らしさを大切にしながら保育できる良さがありますよ。
何よりもやりがいと達成感があります。
どんな保育ができるのか、子どもたちの姿や成長が見られるのか毎日ワクワクしていました。
また、子ども自身の成長を感じられる場面が多く、日々子どもの成長に驚き、喜びを感じていました。
子どもたちと計画した行事を無事に終えられたときには、子どもだけでなく、保育者としての自分自身の成長も感じられましたよ。
ぜひ子ども主体の保育の魅力を知って、楽しんでほしいと思います。

執筆者:ほいコレ 編集部