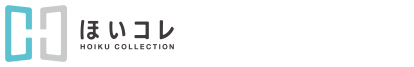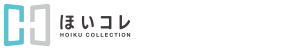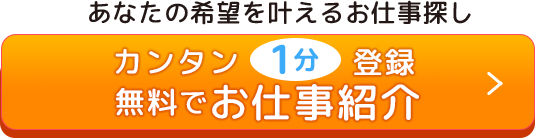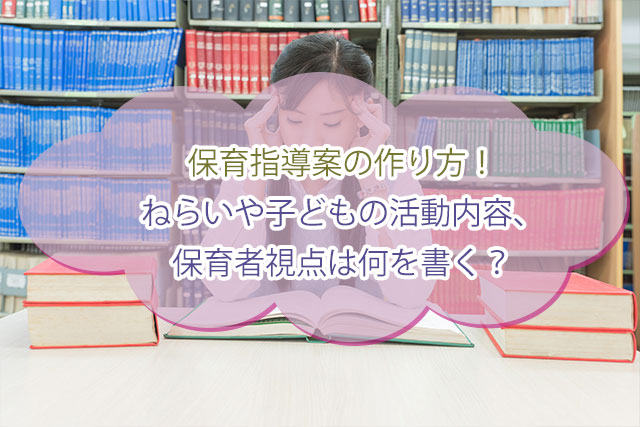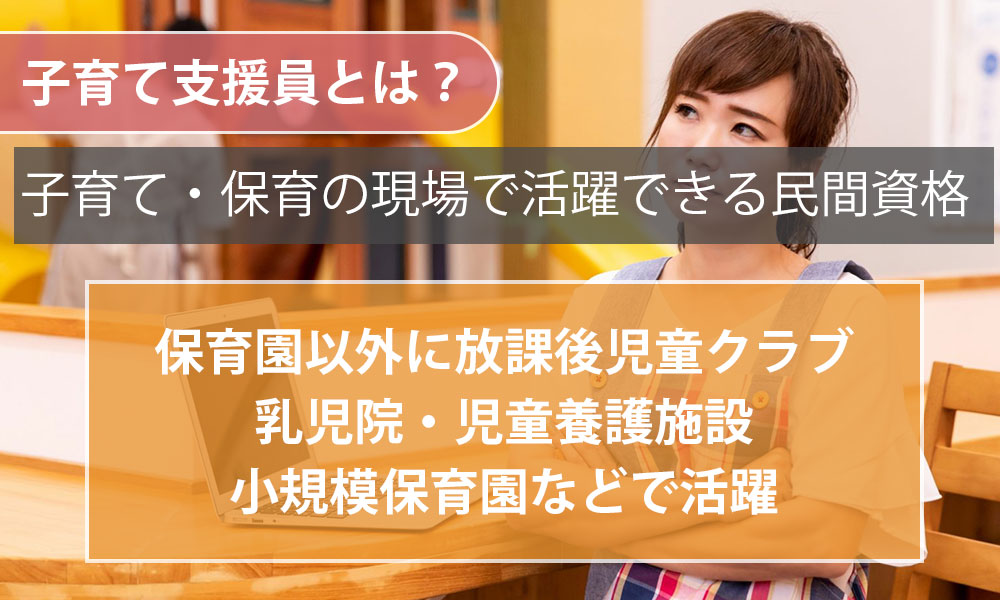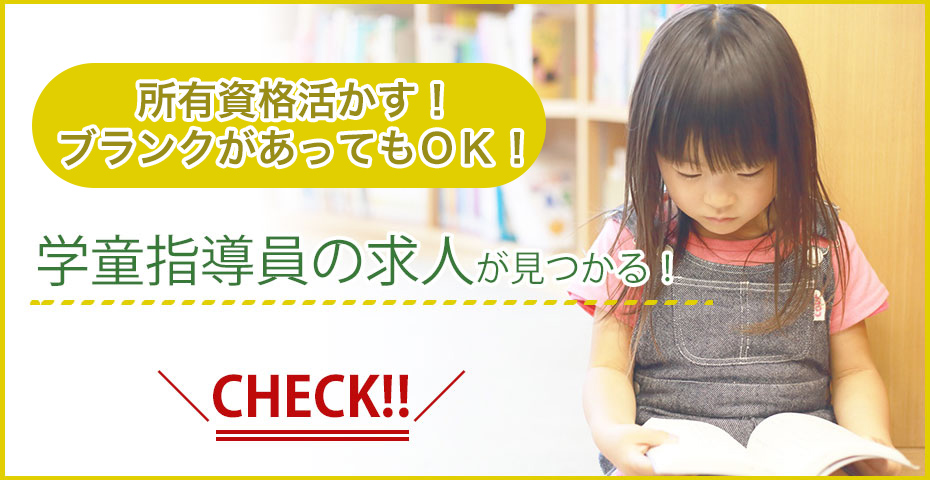2025.3.13
院内保育ってきつい?リアルな仕事内容とやりがいを徹底解説!
1420View
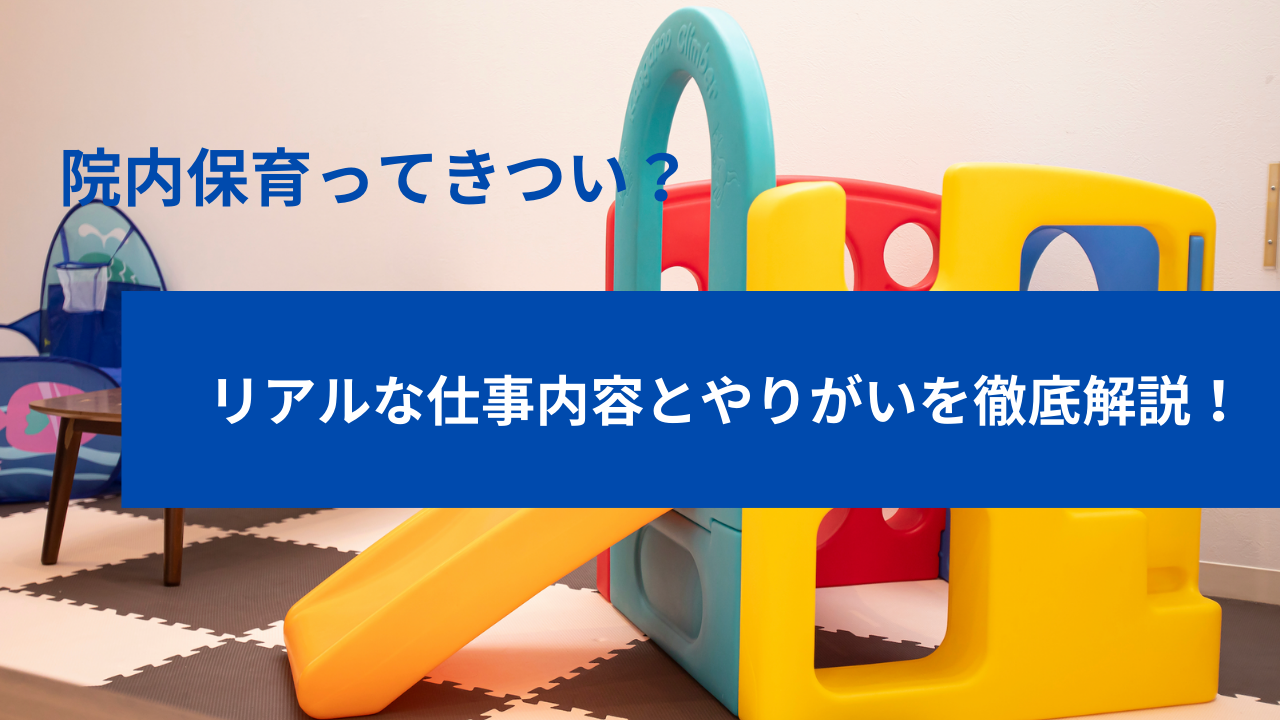
こんにちは。今回の記事では病院内で働く保育士、つまり「院内保育」についてご紹介します。院内保育は医療従事者が安心して働けるよう支える大切な役割を担っており、保育士にとっても魅力があります。
その一方で、課題もあるのが現実です。この記事では院内保育のメリットや注意点を分かりやすく解説し、自分に合った働き方を考えるヒントをお届けします。
• 院内保育士の業務内容
• 院内保育で働くための具体的な方法
院内保育とは何か?
院内保育を簡単に言うと、病院や医療施設で働く医師や看護師などの職員のお子さんを対象に保育を行う施設です。この施設では保育士が日常的な子どものケアや教育を行いますが、一般の保育園と同じ環境ではないことも多く、それが院内保育ならではの特徴を生み出しています。
施設の環境·役割
院内保育は医療従事者の勤務体制に対応するために早朝や夜間の保育を行う点が大きな特徴です。病院内や隣接地に施設があるので保護者にとって安心感が高く、子どもが急に体調を崩した際もすぐに医師に相談できる環境が整っています。
多くの病院では24時間体制が一般的で、それに合わせて院内保育所も「24時間保育」を実施することが多くなっています。これは夜勤や早朝勤務の保護者を支えるだけでなく、医療現場の効率向上にもつながります。
一方で、保育士には柔軟な対応力が求められます。一般的な保育園とは違ってクラス分けや細かい保育計画が少ない分、子ども一人ひとりにしっかり向き合える環境が整っている点は大きな魅力と言えるでしょう。
少人数·家庭的な保育
保育園では多くの園児が在籍する大規模な環境で働くことが一般的ですが、院内保育では異年齢の子どもたちを小さなグループで保育します。少人数制ではより深い関係性を築ける良さがあります。
それだけではなく、保護者と非常に近距離でコミュニケーションが取れる点も院内保育ならではのメリットです。同じ病院という環境で働く保護者との連携は深く、その分信頼関係を強く築けることがあります。
また、保育士自身は保護者の医療業務への貢献を間接的に支えているという大きな社会的やりがいを感じる場面も多いものです。
院内保育士として働くメリット
院内保育士には一般的な保育園勤務にはない独特のメリットがあります。働きやすさや保育士としての充実感など、多方面で大きな魅力があります。ここでは、院内保育士として働く5つの主なメリットをご紹介します。
子ども一人ひとりとじっくり向き合える少人数制保育
院内保育の施設は小規模な場合がほとんどで、1日の定員が30人以下というケースも多々あります。そのため、一人ひとりの子どもとしっかり関係を築き丁寧にケアする保育が可能です。これは、いわゆる大規模保育園では難しい、保育士と子どもとの「深いつながり」を感じられる瞬間が増えることを意味します。
例えば子どもの成長を間近で感じ、「昨日まで一言もしゃべらなかった子が、自分にだけ懐いてくれるようになった」という具体的なエピソードが日常的に起こる環境は、やりがいにつながります。
業務負担が少なく、無理せず働ける
院内保育では、クラスを受け持つことがない場合がほとんどです。「担任」がいないということは、日々の細かな計画や大量の書類記録に追われる心配が少ないということ。一斉活動や運動会、発表会といったイベントも少ないため、行事準備に時間や労力を取られないのも魅力的です。
また、業務時間もシフト制が基本であり、1日あたりの業務スケジュールが安定しています。このため、仕事の終了時間が予測しやすく、残業などが発生する可能性も低めです。
保護者との距離が近く、連絡がスムーズ
院内保育では、子どもの保護者である医療従事者が同じ病院内·施設内で働いています。このため、タイムリーな情報共有が可能です。たとえば、子どもの体調に変化があった場合も、施設内で連絡を取るだけで保護者にすぐ対応してもらえる環境です。一般的な保育園とは異なり、保育士にとっても安心感のある職場と言えるでしょう。
こうした連携が日常的に繰り返されることで、保護者からの信頼が厚くなり、「あなたに子どもを預けて本当に良かった」という声を直接聞ける機会も多くなります。
高待遇が期待できるケースが多い
院内保育士として働く施設の中には、病院が直接運営していたり、委託企業が病院の福利厚生の一環として運営している場合があります。そのため、院内保育士には夜勤手当や早朝手当、加えて交通費補助や住宅手当などの福利厚生が充実しているケースも少なくありません。
特に、数回の夜勤をこなせば、一般的な保育士の収入水準を上回る給与が見込める可能性もあります。実際、収入面での満足度が高い院内保育士は多く、その点は一つの大きなメリットだと言えるでしょう。
やりがいのある社会的役割を感じられる
院内保育士は、ただ子どものケアをするだけでなく、医療現場を支える重要な役割を果たしているのです。医師や看護師など、医療の最前線で働く保護者のサポートをすることで、間接的に社会全体に貢献しているという実感を得られます。
医療従事者が安心して子どもを預けられる環境を提供することは、医療現場で働き続けるための大切な支えとなります。こうした「縁の下の力持ち」としての役割に、誇りややりがいを感じる人も少なくありません。
総合的にみた働きやすさ
院内保育士として働くことは、子どもの成長を身近に感じながら、医療現場のスタッフを間接的に支える社会的意義の高い仕事です。労働時間や業務内容が過度に負担になることは少なく、家庭との両立もしやすい働き方であるため、魅力的な選択肢と言えるでしょう。
見逃せない注意点と課題

どんなに魅力的な職場でも課題や注意すべき点が存在し、院内保育も例外ではありません。働き始めてから「こんなはずではなかった」とならないためにも事前に理解しておくことが大切です。ここでは、院内保育で働く際の注意点と課題について詳しく解説します。
勤務時間が不規則になる場合がある
院内保育は保護者である医療従事者のシフトに対応できるよう運営されており、保育士も基本的にシフト制で勤務します。
夜勤や早朝シフトなど生活リズムが不規則になる場合があります。特に「24時間保育」を実施している施設では夜間勤務が求められることも。若いころは問題なくても、家庭を持ったり年齢を重ねると夜勤の負担が大きくなります。
解決のヒント: 自分の体力や生活スタイルを考慮し、夜勤が少ない職場や夜勤を必要としない求人を探すなど、条件をよく確認しておくことが必要です。
子どもの登園時間·降園時間がバラバラ
一般の保育園では朝の決まった時間に子どもが登園し、夕方にはほぼ同じ時間に降園するのが一般的です。しかし、院内保育では保護者の勤務時間に合わせて子どもが登園·降園するので時間はバラバラです。このため、保育計画やスケジュール作成も柔軟性が求められます。
状況のイメージ 「早朝に数人が登園したかと思えば、その子たちが帰る頃に夜勤対応で新たな子どもが登園してくる」というケースがあり、ある意味では「計画通りにいかないのが当たり前」の環境という点を理解しておかなければなりません。
集団保育よりも少人数特化の対応が多い
院内保育では少人数の異年齢保育が主流です。これは多くのメリットを生む一方で、保育内容が制限されるという点もあります。
例えば、大人数での活動や運動会のようなイベントを催すことが難しくなるため、保育士自身が「準備したことを子どもたちに全力で楽しんでもらう」といった面でのやりがいを感じづらいことがあります。また、年齢別のクラスがないことで活動内容を子どもの個々の発達段階に合わせて工夫する必要があります。
例:製作活動の場合 少人数かつ異年齢なので、1歳の子には「手形スタンプ」、5歳の子には「ハサミで切った形を貼る」といったように、同じ題材でも工夫して分ける必要があるでしょう。
施設設備の充実度に差がある
保育環境についても注意が必要です。院内保育施設は病院内部や併設施設である関係上、園庭がなかったり十分なスペースを確保できない場合も少なくありません。広い園庭で思い切り遊ぶ、といった一般的な保育園のような活動が難しく感じることもあります。
このような制約がある中で、室内遊びや散歩など限られた資源を活用して子どもを楽しませる工夫が大切になります。
子どもの顔ぶれが頻繁に変わる
院内保育では保護者の勤務スケジュールに合わせて子どもが登園するので毎日同じ子どもを預かるとは限りません。「長期間にわたって同じ子どもを育む」といった保護者目線に近い感覚が薄れがちです。
「子どもの成長をしっかり追い続けたい」と考える保育士にはやりがいが感じにくい場合もあるでしょう。
プライベートの調整が難しい場合もある
シフト制勤務という特性から「家族との予定を合わせづらい」「急なシフト変更に対応しなければならない」といった生活面での影響も少なからずあります。家庭を持つ保育士にとっては自分の生活との両立が難しく感じることも。
解決のヒント: 勤務先によっては柔軟なシフト調整ができる場合もあり、求人選びの段階でしっかり確認することが大切です。
課題への向き合い方
これらの注意点や課題を踏まえると、院内保育は「柔軟な対応力」や「工夫する力」が求められる職場であることがわかります。しかし、この環境は保育士としてのスキルが磨かれるのも確かです。
特に少人数保育や変則的なスケジュールに対応する経験は保育士としての成長につながるでしょう。
院内保育が求めるスキルと向いている人
院内保育は一般的な保育園とは異なる環境で仕事をする場です。適応するために特定のスキルや資質が求められる一方で、向き·不向きが非常に明確になる職場でもあります。ここでは、院内保育士に求められるスキルと特に向いている人の特徴について解説します。
院内保育が求めるスキル
高い柔軟性と対応力
院内保育では保護者である医療従事者の勤務シフトに基づいて子どもの登園と降園時間が変わります。このため、「スケジュールや計画通りに進まないこと」に慣れる必要があります。
予定外の子どもの登園があった場合でも混乱せず、冷静にその子どもに最適な保育活動を提供できる柔軟性が求められます。また、異年齢保育で子どもの年齢や性格がバラバラになることも多く、それぞれの発達段階に合った関わり方ができる適応力が必要です。
少人数保育での観察力
院内保育は少人数制であり、一人ひとりの子どもとじっくり向きあえる環境があります。わずかな子どもの変化やニーズを敏感に察知する観察力が重要になります。
いつもは元気な子が普段と様子が違う場合「昨夜しっかり眠れていないのか」「家庭で何か気になることがあったのか」という背景を考えながら、子どもに寄り添った保育を行うことが大切です。
臨機応変なコミュニケーション能力
保護者との距離が近い院内保育では密なコミュニケーション能力が必要です。特に、医療従事者の保護者は忙しい業務の合間に子どもの状況を確認する時間しか取れない場合が多いです。そのため、限られた会話の中で簡潔かつ正確に報告や情報提供ができるスキルが求められます。
また、ときには保護者側のストレスやプレッシャーを察しながら心のケアをする場面も出てきます。
夜勤や変則勤務への耐久力
夜勤や長時間シフトが発生することが多い院内保育では、一定の体力や自己管理能力が求められます。「きちんと休息を取る」「睡眠サイクルを意識して調整する」など、自分の心身の管理をしっかり行えることも大切です。
院内保育に向いている人の特徴
《一人ひとりと丁寧に接したい人 》
子どもの成長をサポートするだけでなく、保護者に安心感を与えたいという方には院内保育は特に向いています。少人数制だからこそ、きちんと子どもや保護者に寄り添う保育ができる環境です。
《柔軟なワークスタイルを楽しめる人》
変則勤務や異年齢保育といった環境を「難しそう」と捉えるよりも、「新しいことに挑戦したい」「工夫すると面白い」とポジティブに捉えるタイプの人には院内保育はやりがいのある職場となるでしょう。
《社会貢献意識が強い人》
医療現場で働く保護者を支えるという間接的な社会貢献に喜びを感じられる人には院内保育の仕事が大変向いています。「自分が行う保育が親を支え、ひいては社会を助けている」と強く実感できる場面が多いのも魅力です。
《チームワークを重視できる人》
少人数の職場では同僚とのチームワークが重要です。情報共有や勤務時間の調整、子どもへの対応などで仲間と協力しながら働ける人は院内保育に向いています。
こんな人には不向きかも?
一方で、院内保育は次のような性格や志向を持つ人には向いていない場合もあります。
・規則的な勤務時間や生活リズムを重視する人
・イベントや大規模な活動が好きで、保育内容にダイナミックさを求める人
・長い期間関わってきた子どもの成長を追い続けることに強い価値を感じる人
こうした方は院内保育以外の保育施設の方が自分らしく働ける可能性があります。
自分に合った働き方を見つけるために
院内保育では子どもや保護者との近い距離感で働けるという大きな魅力があり、柔軟な発想や対応力が発揮できる環境です。一方で、変則的な勤務体系や施設設備の制約など、独自の働き方に向き不向きがあります。
これから院内保育を目指す場合、スキルや性格、ライフスタイルを十分に考慮しつつ、自分に合った職場を見つけることが大切です。
院内保育に挑戦するための第一歩

院内保育士として働くためには事前の情報収集や計画的な準備が大切です。通常の保育園とは違う環境であるため、自分に向いているかを見極めながら進めていくことが成功のカギとなります。ここでは、院内保育士として働くための具体的な方法や注意点を解説します。
求人情報をしっかりリサーチする
院内保育の求人は一般的な保育園の求人より少ない傾向にあります。多くの選択肢を持ちたい場合は転職エージェントや求人検索サイトを活用するのが効率的です。注意すべきポイントは以下です。
チェックするべきポイント
勤務時間: 夜勤や早朝勤務の有無、シフトの柔軟性など。
施設設備: 園庭の有無、活動スペースの広さ。
雇用形態: 正社員、アルバイト·パートのどちらを希望するか。
手当や福利厚生: 夜勤手当、交通費補助などがあるか。
施設によっては院内保育として運営されていても、運営母体が病院そのものではなく外部の業者である場合があります。運営者によって待遇や働き方が違うので、詳細な情報を確認することが必要です。
施設見学を通じて適性を確かめる
求人情報だけでは施設の雰囲気は分かりにくいものです。できる限り施設見学を行い、実際の雰囲気や働く保育士の様子を確認しましょう。
見学時のポイント
・子どもたちがどのように過ごしているか。
・保育士や職場スタッフ同士のコミュニケーションの様子。
・施設の広さや設備の状態。
・保育方針が自分の考え方にマッチしているか。
見学時に自分の働き方や価値観と合致しているかを考えることで、より納得感のある選択ができるでしょう。
履歴書·面接でのアピールポイントを準備する
院内保育での採用面接では保育の経験や資格に加えて、特に以下のポイントをアピールすることが有効です。
アピールするべきポイント
・柔軟な対応力: 異年齢保育や突然のスケジュール変更にも対応できる姿勢。
・観察力と配慮: 少人数保育で一人ひとりに丁寧に関わる力。
・コミュニケーションスキル: 保護者や職場スタッフとのスムーズな連携ができる能力。
自己PRは「これまでどんな場面で工夫をして柔軟に対応したか」という具体例を盛り込むと好印象を与えることができます。
自分に必要なスキルを磨く準備をする
院内保育では幅広い年齢の子どもと関わることが求められるため、異年齢保育のスキルを事前に学んでおくのも良いでしょう。
スキルアップのためにできること
・異年齢保育に関する書籍やオンライン講座に参加する。
・保育雑誌や専門書で製作や細かい遊びのアイデアを増やす。
・コミュニケーションの場での柔軟性を意識して培う。
一部の施設では夜間保育も行うので「夜勤経験者」が有利になることも。経験がない場合でも前向きに「挑戦してみたい」と意思表示をすることで、採用担当に意欲を伝えられます。
ライフスタイルと求める条件を整理する
院内保育の特徴の一つは、シフト制やフレキシブルな勤務時間です。これを前提に、自身のライフスタイルの中で何を重視したいかを整理しておきましょう。例えば以下の点を考慮します。
家庭やプライベートとの両立の可能性。
夜勤があっても問題ないかどうか。
フルタイム勤務かパートタイム勤務か。
条件を整理して無理のない働き方で長く勤続できる職場を見つけやすくなります。
転職サポートサービスを活用する
自身だけで院内保育の求人を探すのが難しい場合、保育士向けの転職サポートサービスや専門のコンサルタントを利用するのも一つの手段です。職場の内部事情や働きやすさまで詳しく知れる場合もあります。
オススメの利用サービス
・保育士専門の求人サイト
・地域で開催される転職フェアや相談会
・病院が直接運営する保育施設の公式サイト
これらを活用することで、自分に適した求人に出会う確率が高まります。
第一歩は慎重かつ積極的に
院内保育士として働くためには自分に最適な職場を見つけるための事前準備が重要です。求人内容、施設見学、自己分析を行い、理想の働き方を具体的にイメージすることが成功への道となります。そして、自分のスキルと適性をアピールする準備を整えることで、新しい環境でのスタートを切る自信が得られるはずです。