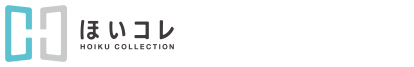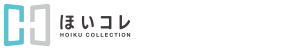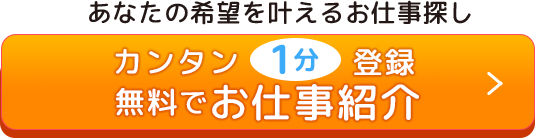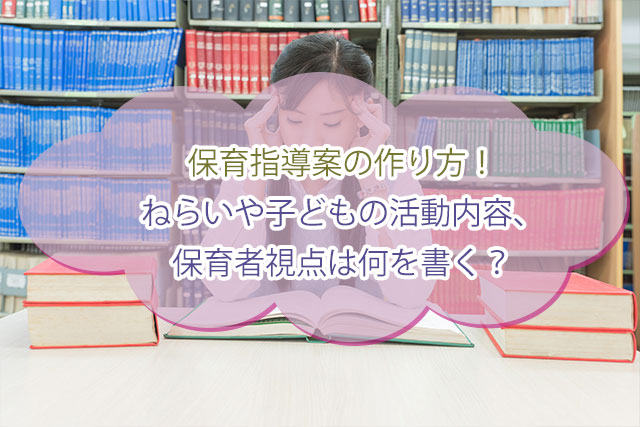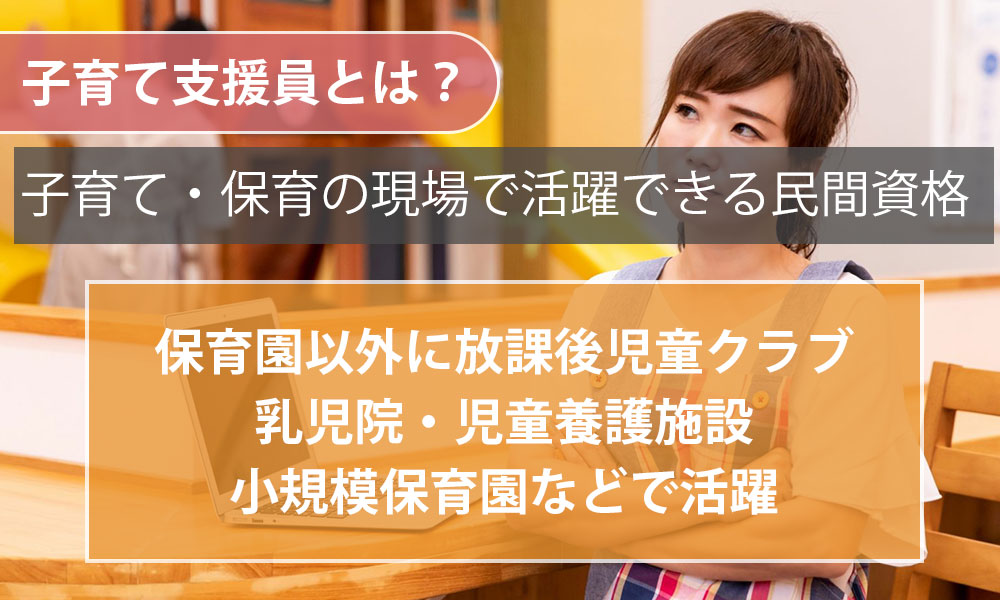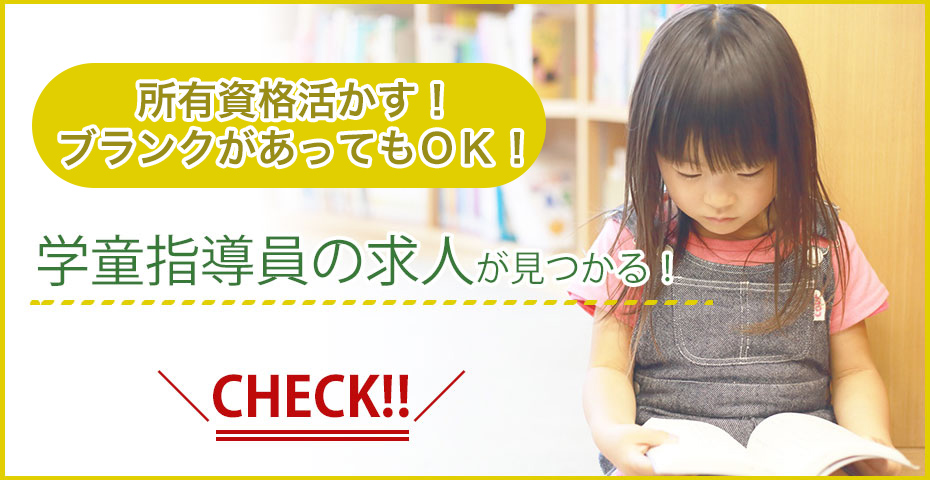2025.3.11
試験なしでも保育士になれる?資格取得のもう一つの道
2831View
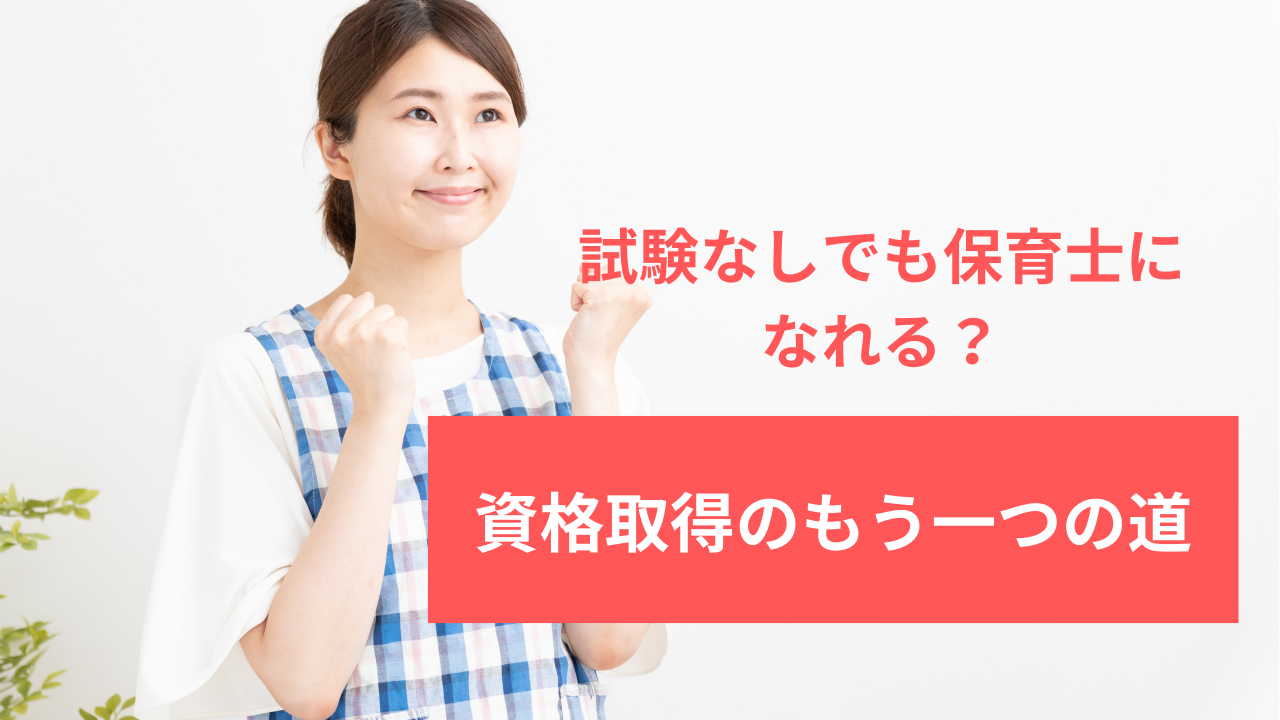
こんにちは。保育士は子どもの成長を支え、社会にも大きく貢献できる魅力的な職業です。実は資格を取得する方法は複数あり、「どのルートを選ぶべきか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では「試験を受けずに保育士を目指す方法」に焦点を当て、その仕組みやメリット・デメリット、試験ルートとの比較を詳しく解説します。保育士の需要が高まる中で、できるだけスムーズに資格を取得したいと考える方に最適な道を選ぶためのヒントをお届けします。
• 取得ルートによるメリットとデメリット
• 資格取得後の未来と可能性
目次
試験を受けずに得られる保育士資格取得方法の概要
保育士資格を取得するための基本ルートは大きく2つあります。一つは【保育士試験を受験して合格する方法】、もう一つは【指定保育士養成施設を卒業して取得する方法】です。
今回のテーマである「試験を受けずに保育士資格を取得する方法」とは、「指定保育士養成施設」を活用するルートのことを指します。これは、都道府県知事が指定した大学・短大・専門学校などで決められたカリキュラムを履修し、必要な単位をすべて取得して卒業することで試験なしで保育士資格を得られる制度です。
このルートの特徴は以下です
試験のプレッシャーがない
筆記試験や実技試験などの保育士試験を受ける必要がないです。試験不合格というリスクを感じることがなくなります。
体系的かつ実践的な学び
指定保育士養成施設では、保育の基礎知識、実習を含む実践スキル、さらには子ども以外への多岐にわたるカリキュラムが網羅されています。保育経験ゼロの方でも基礎から専門的な内容までしっかりと学べるため、現場で即戦力になれるためのスキルを身につけられます。
多様な選択肢
4年制大学から短期大学、専門学校、さらには通信教育を提供している学校もあり、自分のライフスタイルや置かれた環境に合わせて選ぶことができます。
実際に通う期間や学費には差がある
「どれくらいの時間とお金が必要になるのか?」というのは、多くの方が気にされるポイントでしょう。
4年制大学では時間的余裕ができる分、学費が高く、卒業までに通常4年かかる場合がほとんどです。一方で、2年制の短大や専門学校では比較的短期間かつ費用を抑えて資格取得が可能です。ただし、短大や専門学校では学ぶ範囲が深くなかったりや狭いことがあります。
通信教育や夜間学校も選択肢にあります。これらは働きながらでも保育士資格を取れる方法として特に社会人には人気ですが、通学コース以上に自己学習の努力やスケジュール管理が求められることがポイントになります。
誰に向いている方法なのか
試験を受けずに資格取得できるこの方法ですが、特に以下のような方に向いていると言えるでしょう
学ぶ時間をしっかり確保できる方
働きながら学ぶよりも、学生として通学して集中して保育分野を学んでいきたい方。
学費に投資できる余裕がある方
短期的なお金はかかりますが、学ぶことで将来的な就職の道が開くので、学費を「将来への投資」と考えられる方。
試験対策に不安がある方
筆記試験や実技試験へのプレッシャーが大きすぎるという方にとっては、試験のないルートは明確な選択肢となります。
指定保育士養成施設を利用するメリットとデメリット
指定保育士養成施設で資格を取得するルートは、多くの人にとって効率的な選択肢かもしれません。一方で、目に見えないコストや時間の制約も伴います。ここでは、知っておくべきポイントや考慮すべき課題を詳しく見ていきます。
指定保育士養成施設を利用するメリット
1. 試験対策のストレスから解放される
厳しい保育士試験を回避できる点はこのルートの最大の魅力かもしれません。特に筆記試験では全9科目をカバーし、60%以上の得点を求められるため、多くの人が苦労します。しかし、保育士養成施設では試験は不要で、カリキュラムをしっかり履修すれば卒業と同時に資格が得られます。
2. 専門的で実践的なスキルを習得できる
保育士養成施設では座学はもちろんのこと、現場で役立つ実技や保育実習が含まれたカリキュラムが組み込まれています。たとえば、保育実習では実際の保育園や施設で働くための具体的なスキルや心構えを学べます。資格取得後も不安なく現場に飛び込むことができるのです。
3. 施設ごとに多様な学びの選択肢がある
数多くの指定保育士養成施設があり、それぞれ特色があります。
・短期的に学びたい方
短期大学や専門学校で2~3年学べるコース。
・深く学びたい方
4年制大学のコースでは、幼稚園教諭資格などの保育関連の複数資格を同時に取得できる場合もあり。
・社会人や忙しい方
夜間部や通信コースを提供している学校もあり、ライフスタイルに合わせた学びが可能。
4. 就職率の高さ
指定保育士養成施設では、多くの場合で就職サポートがセットになっています。地元の保育施設など施設との強い繋がりがあり、自然と就職活動がしやすい環境が整っているのも強みです。特に地方の学校では地域密着型の求人が多く、卒業生の地元就職率が非常に高い傾向があります。
指定保育士養成施設を利用するデメリット
1. 学費の負担
指定施設に通うには費用がかかります。
・4年制大学:400~500万円
・短期大学:200~300万円
・専門学校:200~250万円
教材費や実習費なども別途必要となり、まとまった出費を覚悟しなければなりません。ですが、奨学金制度や教育ローンの利用が可能な学校も多いため、事前に相談·調べてみるのも有効です。
2. 時間的な制約
学校に通う期間は短くても2年間は必要となります。その間はフルタイムで働くことは難しいと考えた方が良いでしょう。特に家計を支えている方や育児中の方にとって、この時間の拘束は大きな課題となるかもしれません。
3. 選べる学校に限りがある
地方によっては指定保育士養成施設が少なく、通学可能な距離に選択肢がない場合もあります。この場合は通信制の学校を検討するか、通える範囲に引っ越しを検討する必要があるでしょう。ただ、後者は家族やライフスタイルにも影響を与えるので慎重な検討が必要です。
4. 働きながらの両立が難しい場合も
社会人向けの夜間部コースや通信型コースもあるとはいえ、現場実習や指定クラスの出席が求められる場合もあります。「働きながらの資格取得」を目指したい方にとっては、大きなハードルとなる可能性があります。
メリットとデメリット、総合してどちらが有利?

指定保育士養成施設はじっくりと学び、現場で即戦力を目指したい方には非常に適した方法です。その一方で、時間やお金に余裕がない場合や働きながら資格を取りたい場合には試験ルートの方が現実的かもしれません。
試験ルートとの比較:自分に合う選択肢を探す
保育士資格を取得するためには「指定保育士養成施設を利用する方法」か「保育士試験を受験する方法」の二つのルートがあります。
指定保育士養成施設ルートと試験ルートの特徴比較表
|
特徴 |
指定施設ルート |
試験ルート |
|
試験の有無 |
不要(卒業時に自動的に資格が付与) |
必須。筆記試験(9科目)+実技試験 |
|
学費 |
高め(200万円~500万円程度) |
低め(教材費、受験費用で数万円) |
|
所要時間 |
2~4年(通学期間) |
勉強の進捗次第で1回の受験でも合格可 |
|
学習方法 |
学校での座学·実習を中心 |
独学、通信講座、または講習会など主体 |
|
休日/仕事の制約 |
通学時間が必要(フルタイム勤務は困難) |
自分のペースで学習が可能 |
|
資格取得の確実性 |
卒業さえすれば100%取得可能 |
試験の合格次第でリスクや難易度が高い |
|
実践スキルの充実 |
保育実習を通じて即戦力を養える |
現場経験がない状態で受験可能 |
指定施設ルートがおすすめの人
1. 学費や時間に余裕があり、じっくり学びたい人
指定施設では計画的に保育について深く学べる環境が整っています。試験勉強のように独学で「とにかく合格」を目指すのではなく、理論と実践をバランスよく習得できるのが特長です。このため、将来的に保育士として現場で長く働きたい方に特におすすめ。
2. 実技や現場での学びを重視する人
保育士として働くには子どもや保護者と接するためのコミュニケーション能力や実践力が不可欠ですが、指定施設ではこれらを実習の中でしっかり学べます。特に実技作業や現場感覚を身につけたい方には最適な環境です。
試験ルートがおすすめの人
1. 学費を抑えたい人
指定施設での学費は数百万円と負担が大きいため、学費がネックとなる場合は試験ルートが現実的と言えます。試験に必要な教材費や受験料は指定施設への通学費用よりも非常に安いです。
2. 働きながら資格を目指したい人
試験ルートでは自分のライフスタイルに合わせて計画的に勉強を進めることができます。特に、日中フルタイムで働きながら夜や週末を使って勉強しながら資格を目指したいという方に適しています。
3. 短期間で結果を出したい人
試験ルートでは、筆記試験に必要な知識と実技の対策に絞って学べば一発合格も夢ではありません。これに対し、指定施設は必ず2年以上の通学が必要なので、短期間で資格取得を目指す場合には試験ルートが効率的です。
試験ルートの成功ポイント
試験ルートの場合、以下のポイントを押さえて対策すると成功率が上がります。
・受験資格の確認をしっかり
試験を受ける条件に短大卒または高卒の2年以上の実務経験など、一部条件を満たす必要があります。事前に確認しておくとスムーズです。
・教材を選ぶ際は最新情報を許さない
保育士試験では法改正などの最新知識が問われるため、信頼できる最新の教材を活用しましょう。独学が難しいと感じたら通信講座で体系的に学んでも良いでしょう。
・計画的なスケジュールを立てる
試験範囲は非常に広いため、科目ごとにスケジュールを細かく分けて効率的に取り組むことが求められます。
・苦手分野は繰り返し
筆記試験で1科目でも不合格になると次の試験に繰り越しとなります。苦手分野には重点的に時間をかけましょう。
あなたにとって最適なルートを選ぶためには?
最適なルートを選ぶポイントは自分に合った環境や条件、目指したい未来像です。 「時間に余裕があり確実に資格を得たい」という方は指定施設ルート。「早く資格を取りたい、自分のペースで効率よく」という方は試験ルートが良いでしょう。
試験ルートがオススメの理由
保育士資格を取得するには「指定保育士養成施設」か「試験ルート」の二つの方法があります。
これまでにそれぞれのメリット·デメリットや特徴についてお伝えしてきましたが、「学費を抑えたい」「時間を短縮したい」「自分のペースで進めたい」といったニーズを考えると、多くの方にとって試験ルートが現実的な選択肢になることがお分かりいただけたかと思います。
本章では試験ルートを特に推奨する理由とともに、このルートを成功に導く具体的なポイントについて掘り下げて解説します。
1. 学費が圧倒的に安い
試験ルートでは指定施設の学費(200万~500万円)を大幅に削減することができます。教材費や通信講座費用、受験費用を合わせても約10~20万程度に抑えられるのが一般的です。
・独学の場合
市販の参考書や問題集だけでも試験対策が可能です。数万円程度の費用で資格取得の準備が進められます。
・通信講座を活用する場合
資格試験に特化した講座を選べば、学習の手間を省きつつ体系的に知識を習得できます。費用は5~15万円程度ですが、学習効率を考えると十分リターンを見込めます。
2. 時間を短縮できるシンプルな学習プロセス
指定養成施設では卒業までに少なくとも2年(短大/専門学校)かかります。それに対し、試験ルートでは自身の努力次第で1年以内に資格取得も可能です。
例えば以下のような流れが現実的な例です。
・半年で筆記試験を突破するプラン
仮に週15時間程度の集中学習時間を確保できれば、主要科目を網羅し筆記試験を合格圏内に引き上げることが可能です。
・筆記試験合格後すぐに実技対策開始
筆記試験から実技試験まで2~3か月の間があります。この間に実技スキルや苦手分野の対策を重点的に行えます。
3. 働きながら取得を目指せる
試験ルート最大の特徴は自分のライフスタイルに合わせた勉強ができる点が挙げられます。特に仕事と学習を両立したい社会人や、家事·育児を抱えた方におすすめです。
・フルタイムの仕事をしながら夜間や週末に学習
平日は仕事終わりに2時間、週末にまとめて学習時間を確保するスタイルが一般的です。年2回実施される試験日程に合わせてスケジュールを調整すれば、かなりの効率で学習が進められます。
・通信講座を使った柔軟な学習
オンラインでデジタル教材を使う通信講座なら、移動中やスキマ時間も有効活用できて短期集中で効率的な準備が可能です。
4. 一部の科目合格が有効で、ハードルが低い
保育士試験の特徴の一つは、筆記試験で合格した科目は3年間有効(一部条件で5年まで延長)であることです。これにより、科目を一気に全て合格しなくても、計画的に少しずつ試験に挑むことができるため、試験のプレッシャーも軽減されます。
・1年目に4~5科目合格、2年目に残り科目合格
この戦略を取れば、仕事や家庭を抱えている状況でも無理なく受験に挑むことが可能です。
・ピアノなど実技が苦手な場合も選択肢あり
実技試験では「音楽」「造形」「言語」の3種目から選択でき、苦手分野は避けることもできます。ピアノが弾けなくても造形(絵画)や言語(お話の発表)で代替できるのは大きな利点です。
5. 試験勉強が自己成長につながる
保育士試験に向けた学習はそのまま保育現場での実践力に直結します。例えば「子ども家庭福祉」や「保育の心理学」は、深く学ぶことで保護者とのコミュニケーションや子どもの成長理解に役立つでしょう。「保育実習理論」は保育活動の具体的なプランニングに直結します。
自己学習によって身につけた知識やスキルは、保育士として働き始めた際に大きな自信に繋がるだけでなく、現場での即戦力にもなります。
試験ルートを成功に導くためのワンポイントアドバイス
1. 計画的に学習を進める
9科目を片っ端から進めるのではなく、頻出分野や過去問を徹底的に分析して優先度を決めて学習計画を立てましょう。
2. 適切な教材やサポートを利用する
独学で不安を感じる場合は通信講座やサポート校を利用するのも一つの手です。特に合格実績の高い講座を選ぶことで、結果を確実なものにできます。
3. 実技対策は筆記試験後からでOK
筆記試験合格後2~3か月の間にじっくり選択実技を対策できます。苦手意識があっても「選べる試験形式」を活用すれば十分対応可能です。
試験ルートは努力する価値がある選択肢
ここまで述べたように、試験ルートは努力次第で着実にゴールへと近づける現実的かつ効率的な方法です。費用や時間に制約がある場合でも柔軟に対応可能で自力での達成感やスキルの向上も得られます。
どちらの方法でも目指せる未来への第一歩
保育士資格を取得した後にどのような未来が待っているのかを具体的に考えるのは取り組みのモチベーションを保つ上で非常に重要です。資格の取得が「指定保育士養成施設ルート」でも「試験ルート」でも、資格を手にするという目標が達成されればその先には様々な可能性が広がっていきます。
この章では、資格取得後のキャリアや働き方や保育士としてのやりがいや将来展望について掘り下げていきます。
資格取得後に広がるキャリアの選択肢
保育士資格を取得することは保育園での勤務だけを意味するわけではありません。実際には、資格を活かせる職場や役割が非常に多岐にわたります。以下は保育士資格を有することで目指せる主な活躍の場です。
1. 公立·私立保育園
どの地域でも需要が高く、保育士資格が直接活用される代表的な職場です。子どもたちの成長を日々サポートできるやりがいある役割ともいえます。
2. 認定こども園
保育と幼児教育が一体化した施設で、近年ますます増加しています。特に、幼稚園教諭免許も持っている場合はより柔軟な働き方ができます。
3. 病児保育や院内保育
医師や看護師などの子どもを預かる院内保育施設や、病気中·快復期の子どもを預かる病児保育施設での勤務も注目されています。特定の知識や安心感が求められる仕事ですが、その分専門性が高く、多くの保護者に感謝される仕事です。
4. 障害児保育施設·放課後等デイサービス
障害のある子どもたちの成長を専門的に支える施設で働く選択肢もあります。これには特別な知識や研修が必要ですが、大きな社会貢献を感じられる職場です。
5. ベビーシッターや企業内保育
柔軟な働き方を求める方向けに、ベビーシッターや企業内保育士として働く道もあります。個々の家庭や企業の保育ニーズに応えながら、フレキシブルに活躍できる点が魅力です。
働き方の自由度とキャリアの広がり
資格取得後の働き方は個々のライフスタイルや目指すキャリアによって大きく変わります。フルタイムで働くだけではなく、以下のような柔軟な選択肢もあります。
・パートタイムや曜日を限定した働き方
子どもがいる保育士が増える中、時間や曜日を限定した働き方を取り入れる施設も多く存在します。
・独立保育士·フリーランス保育士
特定の保育施設に属さず、フリーランスとして働く選択肢も近年拡大中です。家庭での訪問保育を担う保育士も増加傾向にあります。
・転職の幅広さ
保育士資格を持っていると、福祉分野や教育分野など関連する他の業界への転職もスムーズ。特に幼児教育に特化した企業や教育機関での求人が見つかりやすいです。
保育士として働く魅力とやりがい

保育士という仕事はスキルを活かしながら人々の生活の基盤を支える非常に意義深い仕事です。以下は、保育士として働くことの魅力とやりがいについて挙げたものです。
1. 子どもの成長を間近で感じられる
日々の仕事を通して子どもたちが自信を持って成長していく姿や、小さい成功体験を積み重ねる姿を見ることができます。「先生できたよ」という言葉は保育士にとって何よりの報酬です。
2. 家庭や社会と密接に繋がる
保育士は子どもだけでなく、その保護者とも距離が近い仕事です。また、地域や社会全体を支える一員としての役割を果たす仕事でもあります。
3. 自らのスキルアップに繋がる
人間関係や感情のコントロール能力が鍛えられるほか、資格を活かしてさらなる知識や技術を磨く機会が豊富です。特にキャリアアップを目指す場合、施設長や主任保育士などの管理職を担う道も開けます。
資格を手にした先に広がる未来
資格取得で得られるのは仕事そのものだけではありません。あなた自身の人生も子どもたちや保護者とのつながりを通じて豊かになっていくでしょう。また、スキルを積み重ねることで専門職としての地位や信頼度もアップしていきます。
保育士はただの仕事ではなく、自分の生き方そのものを成長させる職業であり、「人のために」というやりがいにあふれています。
まとめと次のアクション
ここまで、育士資格を取得するためのルートを徹底的に比較し、実際に資格を取得した後の未来についても考察してきました。最後に、重要なポイントを振り返りながら、これから保育士を目指すあなたに向けて具体的な次のアクションプランを提案します。
保育士資格取得のルートを振り返る
今回取り上げた2つの選択肢、それぞれの特徴と魅力を再確認しましょう。
指定保育士養成施設ルート
【メリット】:確実に資格を取得でき、体系的に学べる
【デメリット】:学費が高く、通学期間が必要
【適している人】:余裕を持って学び、手厚い実習や就職サポートを受けたい方
試験ルート
【メリット】:費用を抑えられ、短期間で資格取得が可能
【デメリット】:試験のプレッシャーがあり自己管理が必要
【適している人】:働きながら取得を目指す方や自己学習に自信のある方
自分に合ったルートはこれで見つかりましたか?最も重要なのはあなた自身の状況やライフスタイルに合った方法を選ぶことです。どちらも目標は「資格を手にする」こと。同じ目的地でも道筋は多様にあります。
資格取得への一歩を踏み出すためのアクションプラン
目標へ向けて最初に取り組むべきアクションは以下。
1. 受験資格を確認する
試験ルートを選ぶ場合は受験資格(学歴や実務経験)を満たしているかどうかを事前に確認しましょう。必要条件を満たしていなければ、まずは実務経験を積んだり学歴を整える準備を進めましょう。
2. 学費や時間を計画する
養成施設ルートを選ぶ場合、2~4年間分の学費·生活費をどう確保するか考える必要があります。一方で試験ルートは学習に使える時間や教材·講座費を見積もり、スケジュールや予算をきちんと計画しましょう。
3. 効率的な学び方を選択する
試験ルートの方は以下の方法を検討すると良いでしょう。
・市販教材や過去問を購入して独学
・通信講座や学習アプリでサポートを受ける
・スキマ時間を使った効率的な勉強(オンライン動画を活用するなど)
また、自己学習に不安がある場合は地域の勉強会やスクールなどを探してみると心強いです。
4. 試験日程に合わせたスケジュール作成
特に試験ルートを選んだ場合、最初の試験までにどの程度の学習時間を確保する必要があるかを把握して逆算してスケジュールを組むことが重要です。半年~1年の期間で目標を達成するため、科目別の計画を設定して取り組みましょう。
5. サポートを活用しながら進む
養成施設を選んだ方も試験ルートの方も、ぜひ周りの支援を活用してください。奨学金制度や学費援助は必ず調べましょう。また、学習中の悩みや突破できない壁にぶつかった場合は講座のサポーターや同じ目標を持つ仲間と情報交換をすることが大切です。
保育士資格取得後の未来を描く
資格を手にすることはゴールではなく新しいスタートです。以下のリストを思い出してください。
・キャリアの幅広さ:保育園だけでなく多様なフィールドで活躍可能
・柔軟な働き方:パートタイムやフリーランスの選択肢
・自己成長と社会貢献:子どもたちや地域社会を支え、自分自身も価値を高められる職業
保育士が担う役割は今後ますます重要になっていきます。資格を取った自分の未来を大切にイメージして次のステージを目指してください。
最後に
「試験を受けずに保育士資格を目指す方法」という疑問に対して明確な選択肢を提示しながら、試験ルートの可能性と魅力についても詳しく解説しました。どちらを選んでも必要なのは「一歩を踏み出す勇気」と「継続する努力」です。
あなたが保育士資格を手にし、子どもたちや社会を支える道へと進む一助となれたなら幸いです。この学びはあなた自身や未来のお仕事環境、さらにその周りの全ての人々をきっと豊かにしてくれるでしょう。
さあ、今すぐ最初の行動を起こしてみてください