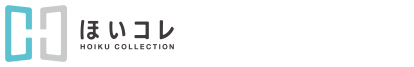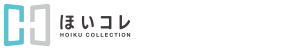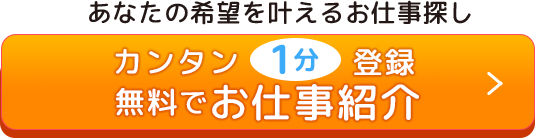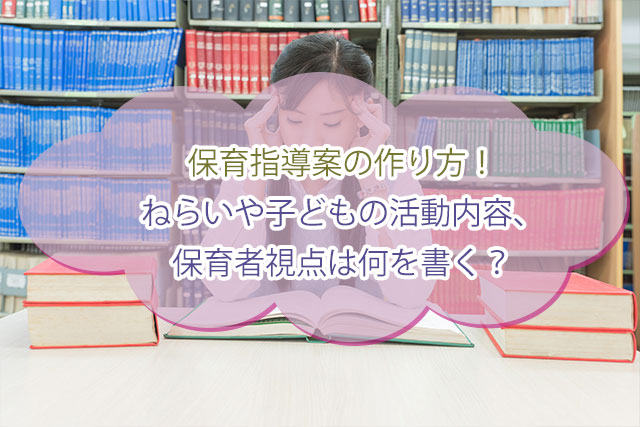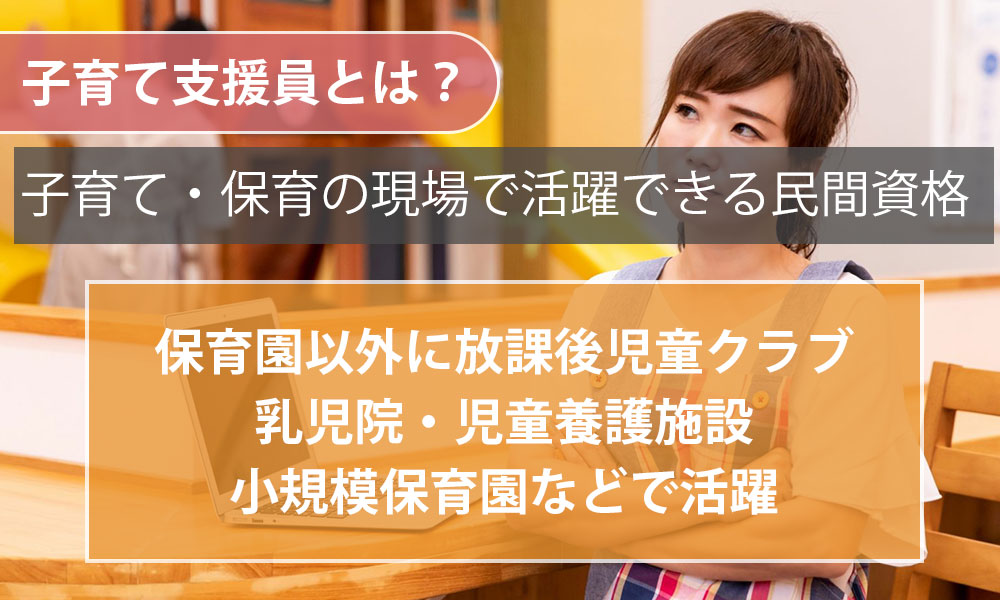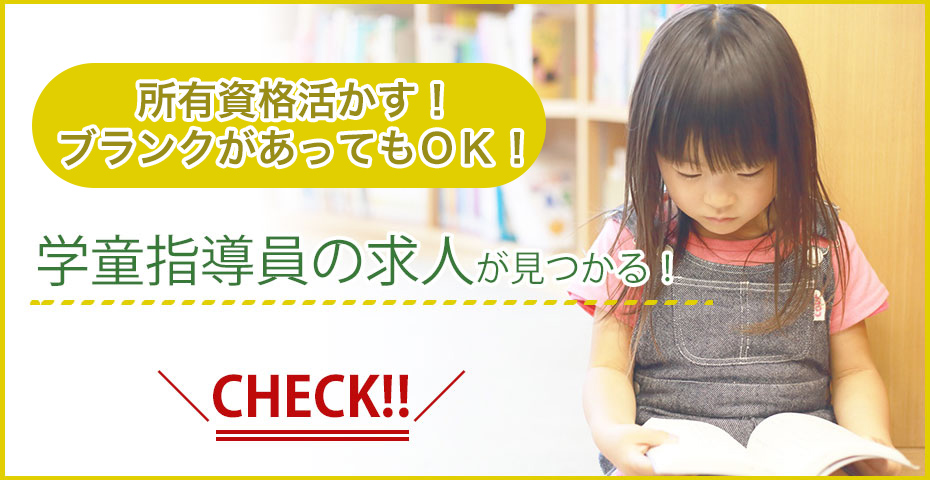2025.1.29
保育所等訪問支援ガイドライン(令和6年7月)が保育士さんに伝える新しい希望
3036View

こんにちは。このページへたどり着いたあなたは、障害のある子どもへの支援方法を学びたい保育士さん、または保育に携わる方かもしれませんね。
保育士として日々の業務に取り組む中で、子どもたち一人ひとりのニーズに応えることの難しさに直面していることでしょう。そして「自分の支援が本当に役立っているのだろうか」と、心細さや悩みを抱えることもあるのではないでしょうか。
今回は、そんな保育士さんに向けて令和6年7月に発行された「保育所等訪問支援ガイドライン」を詳しく解説します。
このガイドラインは特に障害のある子どもたちへの支援の在り方を専門的に示したもので、あなたの日常の業務を少しでも軽くし、より効果的な対応を実現するための一助となる内容です。
• 現場の保育士として実践できる具体的な支援方法の知識
• 保育士としての気持ちを支える考え方や連携のアプローチ
これを読み終わる頃には、今まで抱えていた課題を前向きにとらえ、何をすれば良いかが明確になるでしょう。未来を共に育むための一歩として、ぜひ読み進めていってください。
目次
保育所等訪問支援とは?その定義と役割

最初に、保育所等訪問支援がどのような目的を持ち、保育士さんの業務にどう関わるものなのかを簡単に整理しましょう。
保育所等訪問支援とは、障害を抱えた子どもたちが保育園や幼稚園、学校など集団生活に適応できるよう支援を行う制度です。この支援には子ども本人だけでなく、集団を形成する他の子どもたち、施設職員、そして子どもたちの保護者への働きかけも含まれています。
さらには保育士が行う日々の業務をサポートし、障害に対する理解を深めるための専門家との連携が求められる点が大きな特徴です。この制度はただの「手助け」だけではなく、1人ひとりの子どもの潜在的な能力を引き出す、いわば成長の可能性を広げるためのサポートとして重要です。
ガイドラインが目指す「基本理念」
このガイドラインで何度も強調されているのが「すべての子どもが幸せに生きられる社会」を目指す理念です。
その中でも以下の5つのポイントは特に現場で意識しておきたい指針となります。
• 合理的配慮の提供:発達の特性に応じた対応が求められる
• 子どもの内なる力を育む支援:意欲や自信を育てる姿勢が重要
• 包括的な支援:子ども本人以外にも家族全体を巻き込む対応
• 未来に向けた環境作り:地域参加の促進と障害に対して偏見のない環境作り
• 常に進化する支援方法:訪問計画の習熟と都度レビュー
これらの方針は、現場の保育士さんとして子どもたちと関わる際に、具体的な一日の行動計画にも影響を与えます。
ガイドラインは、ルールや規律ではない「子ども自身の幸福と未来」につながる柔軟な対応を広く後押しするものだといえますね。
サポートの具体例:子どもに行う支援と職員への助言
具体的な支援内容を知ることは、そのまま明日からの実践に生かせるものです。このガイドラインでは、支援の対象を「子ども」「職員」「家族」の3つに分け、それぞれに適したアプローチを提案しています。
子どもに行う支援
まず、子ども支援の目的は、彼らが安心して集団生活に適応し、将来的に社会に参加するための力を育てることにあります。具体的には以下のような内容が挙げられます
• 安心した環境作り
子どもがリラックスして過ごせる環境を整えることが第一歩です。その子にとって刺激が強すぎるものを取り除くなど、現場での少しの工夫が大きな成果を生むことがあります。
• 遊びを通じた発達支援
遊びを通して対人スキルや身体的スキルを学ぶ場を提供します。例えば、絵を描く活動を通じて表現力を養う、またはソーシャルゲームで他者と協力できる喜びを教えるなど、遊びの力を活用しましょう。
• 日常生活動作の指導
着替えやトイレ、食事などの基本的な日常動作を練習し、子どもが自己管理の力を少しずつつけられるようになります。
職員に対する助言
職員への支援は、子どもへの直接的なアプローチだけではなく、支援全体を効率よく進めるためには欠かせない要素です。訪問支援員による助言内容としては
• 障害特性の説明
子ども一人ひとりの特性を理解し、その子に適した接し方を伝えることは重要です。例えば、視覚に訴える方が効果的である場合には絵や図を使うといった具体策を提案できます。
• 環境の調整
保育室内のレイアウト変更や学習スペースの設定など、物理的な環境の改善提案も効果を発揮します。他の子どもたちの動きや声が気になる場合には、柔らかなパーテーションを使用するといった実例を挙げられるでしょう。
• 行事の準備支援
運動会や学習発表会などで、個別の子どもがどのように馴染みやすくなるか、例えば本人が主役級の役割にならなくても参加感を持てるような配慮が具体的に求められます。
どうすれば他のメンバーと一緒に過ごしやすくなる環境を作れるかを、一緒に考えるスタンスを持つことが大切です。
家族ケアも重要!親子の信頼を築く方法
ガイドラインは、子ども本人だけでなく、家族全体をサポートすることの重要性を説いています。子どもの発達を安定させるためには、家族が安心して子育てを行える状況を作り出さなければなりません。
家族支援の方法
• 保護者の話に耳を傾ける
日々の相談相手として、保護者の不安に共感しつつ専門的な助言を行うことが求められます。難しいアドバイスをする必要はありません。「頑張っていますね」と一言添えるだけでも大きな励みになることがあります。
• 子どもの特性や成長を共有する
訪問支援で得られたフィードバックを分かりやすく伝え、親としてどのように接することでより良い結果を引き出せるかを具体的に言葉で伝えます。
• 全体の中で家族の役割をサポートする
家族が子どもの特性を受け入れ、良い影響をもたらす存在になるためには継続的なサポートが欠かせません。「そばにいる安心感」が何よりの支援であることを強調しましょう。
訪問頻度と時間:現場で役立つ実践的な知識
保育所等訪問支援のガイドラインには、おおよその訪問頻度や時間の目安が示されています。しかし、すべてのケースに一括りの対応が適しているわけではありません。
訪問頻度
ガイドラインでは、2週間に1回、または月に2回程度が基本の目安として示されています。ただし、初期段階で環境に馴染む必要がある場合や、緊急性が高い場合には頻度を増やす必要があることも強調されています。
訪問時間
一般的な目安として、1回あたり1時間程度を想定されています。これには子ども本人のケアに加え、施設職員とのカンファレンスも含まれます。ただ短すぎても十分な支援にならないため、個別の状況に応じて柔軟な対応が重視されています。
これにより、保育士さんが感じる「訪問が定型化していないか?」という不安も解消され、同時に支援がより現実的で効果的なものとなるでしょう。
次に、計画の作成からモニタリングに至るプロセスがどのように展開されるのかをお伝えし、さらに支援の質を高めるために使えそうなアイデアを具体的に掘り下げます。
支援計画の作成から改善まで:適切なモニタリングの重要性

保育所等訪問支援の効果を最大限に引き出すためには、綿密な支援計画とその都度の見直し(モニタリング)が欠かせません。ただ一度作成した計画に頼りきるのではなく、子どもの成長や環境の変化に合わせて微調整を行うことが求められます。
支援計画を作るプロセス
支援計画の作成は、障害児相談支援事業所と訪問支援事業所が連携して行います。以下が主なプロセスです
1. アセスメントの実施
o 子ども本人や保護者、訪問先の保育施設職員の声を拾い、現状のニーズや課題を明確化します。
o 子どもの発達特性、家族の要望、訪問施設の現場状況を観察し、具体的な注力ポイントを設定します。
2. 支援目標の明確化
o 長期的な目標(例:3ヶ月後に集団活動に馴染む)と短期的な目標(例:給食中、一定時間席についていられる)を明確に設定します。
o 「支援の成果をどう判断するのか?」を具体的な行動や状況で定義することが重要です。
3. 具体的な支援内容の設計
o 設定された目標を基に「誰が」「いつ」「どのように」支援を進めるのかを詳細に記載します。
o 訪問頻度や時間も、この段階で決める必要があります。
4. 保護者との合意形成
o 作成した計画を保護者に丁寧に説明し、合意を得たうえで実行に移します。
o 保護者が「自分もこの計画に参加している」という感覚を持てるようにする工夫が大切です。
モニタリングで計画を進化させる
計画実施後は、その結果を振り返り、改善点を洗い出すモニタリングが重要です。
これにより、支援が常に効果的である状態を保つための土台ができます。モニタリングの際には以下を確認します
• 設定した短期目標や長期目標に対する達成度
• 子どもや保護者の状況変化や新たな課題
• 訪問先施設との連携状況
モニタリングを行うタイミングも柔軟に設定し、必要に応じて保育士や訪問支援員同士で会議やカンファレンスを実施することが推奨されます。
保育や教育現場との連携:最適な接し方とは
障害を抱えた子どもが集団生活に馴染むためには、現場の状況と支援員の方針が合致していることが重要です。いかにして現場の保育士や教育者と良好な関係を築き、支援の輪を広げていくのか――これが実は大きな鍵となります。
現場との関わり方
1. 信頼関係の構築
お互いに相談しやすい環境を整え、支援員が「現場の味方」であることを意識付けます。訪問時には支援計画や進捗状況を共有し、現場の職員が持つ課題を一緒に解決していく姿勢を示すことがポイントです。
2. 具体的な提案と助言
例えば、「この子には静かなスペースが適しています」「朝の自由時間に簡単な準備運動を取り入れると良いかもしれない」など、具体性のある提案が相手の信頼を得るきっかけになります。
3. 保育の質を向上させる取り組み
障害のある子どもたちに対する適切な接し方や支援方法について、現場のスタッフにスキルを共有することも重要です。例えば、研修や勉強会を設けることで、職員全体が支援の意図を理解しやすくなります。
資質向上のための研修と人材育成
訪問支援を提供する保育士や支援者自身がスキルを高め続けることも、ガイドラインでは大切にされています。環境や障害特性が多様化する中で、常に新しい知識とスキルを吸収し、実践に反映する姿勢が求められるのです。
スキル向上の取り組み
• 自治体主催の研修会への参加 専門性を深めるために、自治体や障害者支援センター主催の研修に定期的に参加することが推奨されています。
• 事業所内での勉強会開催 実際の支援現場で得られた経験を共有し合い、相互に学ぶ機会を設けましょう。「失敗から学ぶ」ことで、次に同じ課題が起きた際に活かせるノウハウが蓄積されます。
• 専門書や資料を活用 支援計画作成や新しい支援手法に関する専門書を定期的に読むことで、知識をブラッシュアップします。例えば、発達障害など特定の障害に特化した資料を揃えておくだけでも役立ちます。
心掛けたい姿勢
• 自分自身も「成長する当事者」として学び続ける意識を持つ
• 他者の意見やフィードバックを謙虚に受け入れ、柔軟な対応力を養う
• 最善の支援を提供するために、常に現状に満足せず前向きに取り組む
次は、安全管理やプライバシー保護といった支援環境を守るうえで大切なポイントを見ていきます。保育士さんとして現場での安心感を確保するための実践方法も盛り込んでいきますので、引き続きお読みください!
安全管理とプライバシー保護:支援環境を守るためのポイント
保育所等訪問支援を行ううえで、子どもの安心感を確保し、保護者や施設との信頼関係を築くためには、適切な安全管理とプライバシー保護が欠かせません。
これは特に現場で働く保育士や支援員にとって、不安要素となる部分でもあります。この章では、具体的な対応例を挙げながら、モラルを守りながら効果的な支援を行う方法を探っていきます。
安全管理の基本
1. 物理的な安全の確保
訪問支援の場合、子どもが利用する施設内の環境をチェックし、転倒や怪我のリスクが少ない環境を整えることが重要です。例えば、角の尖った家具にはコーナーガードを付け、遊具の配置についても子ども同士の衝突を防げる動線を意識します。
2. 非常時の対策を共有
火災や地震、怪我などの緊急時にどのように対応すべきかを施設スタッフと事前にすり合わせておきます。また、支援員自身も施設内の避難経路や緊急連絡先を把握し、有事の際に適切に行動できる準備が必要です。
3. 感染症対策
子どもの免疫が弱い場合もあるため、支援に携わる際は基本的な手指消毒やマスクの着用、体温の確認などを徹底して行いましょう。また、施設側の感染症対策ポリシーに従うことも重要です。
プライバシーを守るために必要な配慮
1. 情報の取り扱いの徹底
子どもの個人情報や支援内容については、厳密に取り扱うことが求められます。ガイドラインでは、以下のような項目が特に重視されています
o 訪問中に得た情報を他者に漏らさない
o 支援内容を報告する際、必要以上に子どもの特性や状況を共有しない
o 記録や書類は適切に管理し、不要な場合には速やかに廃棄する
2. 写真や映像の取り扱い
活動の記録として写真や映像を撮る場合、必ず保護者の同意を得てから行います。また、それらを外部に公開することが許されている範囲を確認することが必要です。
3. 子ども自身への配慮
プライバシーとは個人情報だけでなく、子どもが「尊重されていると感じられる環境」を作ることも含まれます。例えば、気持ちを尊重する声掛けや他児との関係性における配慮が大切です。
安全管理とプライバシー保護の実例
A君という例
発達障害の特性で音に敏感なA君の場合、訪問時は大勢の子どもたちが集まる場所を避け、あらかじめ静かなスペースが用意されていました。事前のカンファレンスで施設の安全対策も確認できたことで、トラブルなく支援を進められたのです。
また、支援内容の報告には、A君の特性や行動を簡潔かつ必要最低限に記載することで、本人のプライバシーも守られました。
訪問支援成功の鍵とは?私たちにできること
最後になりますが、保育所等訪問支援を成功させるための重要なポイントをまとめます。このガイドラインの根底にあるのは、「多様な主体が協力し、子どもを中心に据えた環境づくりをする」という考え方です。
成功の鍵
1. 子どものニーズを最優先に考えること
一人ひとりの子どもが持つ特性や可能性を理解し、その子に合った方法を常に模索する意識を持ちましょう。
2. 関係者全員での連携を強化
支援員、保育士、家族の間で情報共有を徹底し、一つのチームとして子どもを支える精神が欠かせません。対話を大切にし、お互いに意見を交換しながら取り組む姿勢が重要です。
3. 柔軟性を持つ
訪問施設や子ども自身の状況は日々変わることが多いため、計画だけにとらわれず、状況に応じて柔軟な対応を取る意識を常に持ちましょう。
最後に伝えたいこと
障害を抱えた子どもたちがどのように困難を乗り越え、彼ららしい笑顔を取り戻せるか―その助けとなるのが保育所等訪問支援の役割です。この支援のプロセスは、関与する全員が協力し合い、一緒に成長していける素晴らしい機会でもあります。
あなたの知識や努力が、子どもたちの未来を照らす一歩に繋がるかもしれません。
その大切な役目を担う訪問支援員や保育士として、自信を持って明日からの現場に向き合ってみてください。きっと、あなた自身も新たな学びや喜びを得られるはずです。