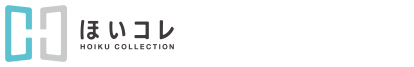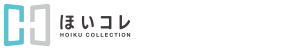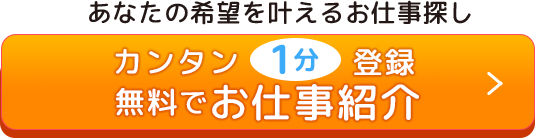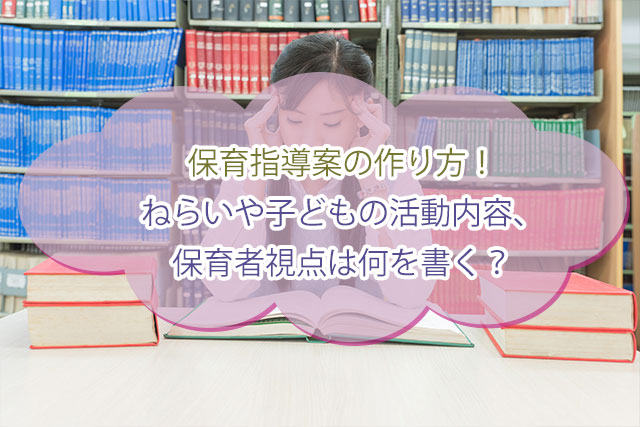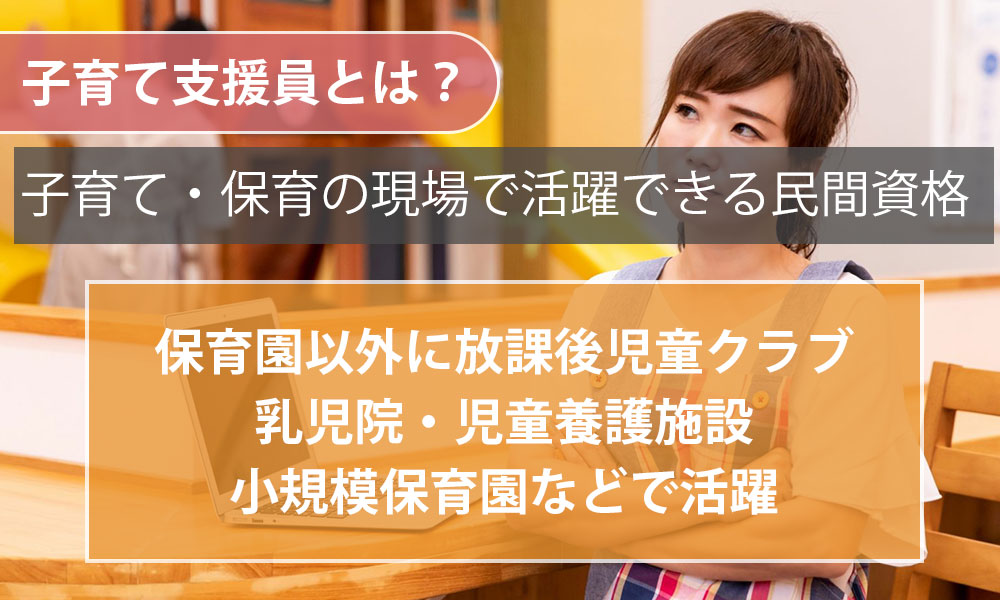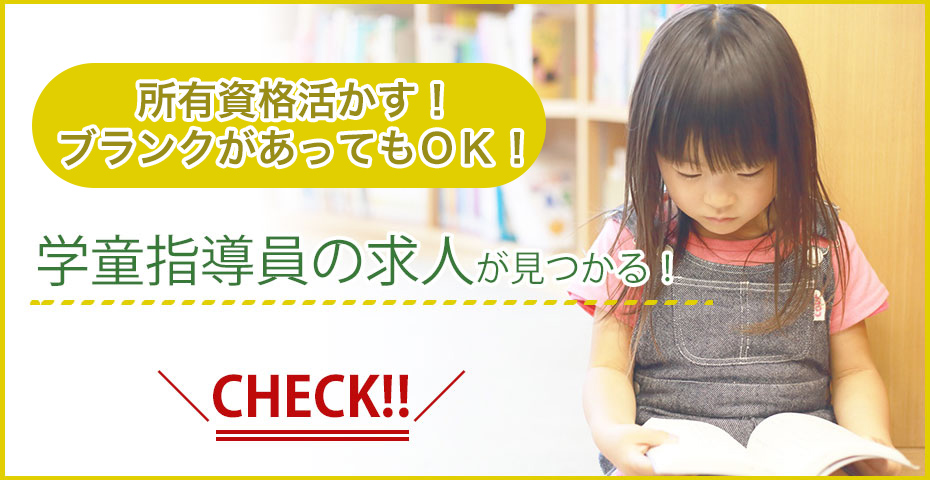2025.4.7
保育士の年収徹底解説|柔軟な働き方『派遣保育士』で高収入を目指す
90View

こんにちは!保育士として働いている方、またはこれから目指す方へ。保育の仕事はやりがいがある一方で、年収や働き方について悩むことも多いですよね。
この記事では、保育士の 平均年収 や 働き方の選択肢 をわかりやすく解説!さらに、柔軟な働き方 と 高収入が期待できる派遣保育士 についてもご紹介します。「もっと自分に合った働き方を見つけたい!」という方は、ぜひ参考にしてください。
保育士は子どもたちの未来のために重要な役割ですが、月々の給与が高くないことや労働時間の長さから続けるのが難しいと感じる人も多いでしょう。その一方で、収入アップのためのキャリア形成や資格取得、派遣保育士としての柔軟な働き方など、新たな道も広がっています。
- この記事で分かること• 保育士全体の平均年収と、働き方・勤務先ごとの収入の違い
• 年収を上げるための具体的な方法や注意点
• 派遣保育士としてのメリットと可能性
これから保育士として働くか迷っている方、すでに働いているけれど よりよい働き方を模索している方にとって、実践的で役立つ情報をお届けします!
平均年収から見る保育士の現状
保育士の仕事は子どもたちの成長を支えるやりがいのあるものですが、収入面の課題があるのも事実です。まずは、保育士の平均年収について詳しく見ていきます。ここで、一人ひとりのキャリアアップの参考になる現状をしっかり把握しておきましょう。
保育士の平均年収はいくら?
令和3年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、保育士の平均年収は約382万円です。この金額は、他の職種と比較してそれほど高くはありません。
全業種の平均年収は約450万円(国税庁の調査による令和2年のデータ)と比べると、保育士の年収は日本の平均より約70万円ほど下回っています。
しかし、皆がこの金額を受け取っているわけではありません。年収は大きく以下の要因によって変わります:
・働いている施設の種類(公立・私立、小規模園・認可園)
・勤務形態(正社員・パート・派遣)
・勤続年数や役職
働き方による収入の違い
保育士の働き方には、正社員、パート、派遣など様々な選択肢があります。それぞれの年収を以下に整理してみました。
| 働き方 | 平均年収(目安) |
| 正社員 | 約374~400万円 |
| パート | 約185万円 |
| 派遣 | 約300~360万円 |
| 公立勤務 | 約430~450万円 |
| 私立勤務 | 約350~380万円 |
正社員は安定した収入や充実した福利厚生が魅力ですが、残業や責任が伴うことも。一方、パートや派遣は時給制で柔軟に働ける反面、収入は勤務時間に左右されます。
また、公立保育士は地方公務員のため、手当や福利厚生が充実し、安定した待遇を受けられる傾向があります。一方、私立保育士は施設ごとに給与体系が異なり、待遇に差があることも特徴です。
平均年収と生活のリアル
先ほど述べた平均年収382万円で生活をイメージすると、一人暮らしはできますが余裕があるとは言えません。特に都心で生活する場合は家賃や交通費が高額になることを考えると、家計にシビアな管理が求められます。
また、家庭を持つ保育士にとって、保育時間が長く保育士自身が子どもの送り迎えをしづらい状況も課題のひとつです。
保育士給与改善の進展
ここ数年、国や自治体で保育士の給与を改善するための施策が導入されつつあります。例えば、処遇改善手当や住宅手当として支給される「借り上げ社宅制度」などです。
積極的に働く自治体や施設を選ぶことが収入アップに直結します。

年齢・役職で見る給与の変化
保育士の給与は年齢や経験年数、そして役職によって変わります。ここからは、年齢層ごとの平均年収や役職に就いた場合の給与増の可能性について紹介します。保育士として働く方がキャリアプランを描く上で、参考になる情報をお届けします。
年齢別の平均年収
保育士の給与は年齢に伴って徐々に上がり、特に経験を積むことで確実な収入アップが期待できます。「令和2年 賃金構造基本統計調査結果」に基づくデータをもとに、年齢ごとの平均年収をまとめました。
| 年齢層 | 平均年収 |
| 20~24歳 | 約300万円 |
| 25~29歳 | 約350万円 |
| 30~34歳 | 約370万円 |
| 35~39歳 | 約380万円 |
| 40~44歳 | 約390万円 |
| 45~49歳 | 約392万円 |
| 50~54歳 | 約430万円 |
| 55~59歳 | 約430万円 |
| 60~64歳 | 約395万円 |
| 65歳以上 | 約350万円 |
特徴とポイント
若い世代では比較的低めですが、30代以降からは収入が安定して増える傾向があります。50代の前半でピークに到達するケースが多く、役職による手当もこの年代が影響を受けやすいです。
また、60代以降の年収が大きく下がる理由は、退職後に非常勤やパートとして働くケースが増えることです。このため、若い世代のうちにキャリアアップや収入増加の手段を模索することが大切です。
役職ごとの収入増加
保育士として働く中で、勤続年数が増えると役職に就くチャンスが多く現れます。主任保育士、副園長、園長などの役職につけば、基本給に加えて役職手当が支給され、年収が大幅に増加する可能性があります。
以下は役職ごとの平均年収です:
| 役職 | 平均年収(公立) | 平均年収(私立) |
| 主任保育士 | 約590万円 | 約460万円 |
| 園長・施設長 | 約650万円 | 約640万円 |
特に公立保育所で主任や園長職を目指す場合、地方公務員としての給与形態に準じ、退職金や年金などの福利厚生を含めると、さらに恩恵を受けることができます。ただし、公立での役職を得るには競争率が高く、採用試験などのハードルがあります。
キャリア形成の道
保育士として給与を上げるための具体的なキャリア形成について、いくつかポイントを挙げます。
1. 資格取得のメリット:
保育士としての専門性を高められる資格(例:幼稚園教諭免許やリトミック指導員など)を取得すれば、資格手当や昇格のチャンスが広がります。
2. キャリアアップ研修の活用:
厚生労働省が導入している「キャリアアップ研修」を受講することで、新設の役職に就くことが可能に。この仕組みを利用して、月4万円程度の処遇改善が期待できる場合も。
3. 地域の特例制度を活用:
地域によっては保育士支援の一環として給与を上乗せする制度が整っている場所もあります。(例: 家賃補助や独自の手当制度)
どう動けば収入アップが見込めるのか?
収入が上がる平均的な年齢や勤続年数を参考に、自分が今どのステージにいるのか確認しましょう。そして、努力を積むべき方向を明確にすることが重要です。特に役職による大幅な収入増加が期待できるため、積極的にチャンスを狙うのも選択肢です。
公立保育士と私立保育士|どちらを選ぶべきか?
保育士を目指す方、あるいは働き方を見直したいと考えている方にとって、「公立保育士」と「私立保育士」のどちらが自分に合うかを理解することは給与や働きやすさの観点で重要です。それぞれの特徴とメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
公立保育士の特徴
「公立保育士」とは地方自治体が運営する公立保育所で働く保育士のことで、そのほとんどが地方公務員にあたります。給与体系や福利厚生は地方公務員の基準に準じており、安定性が大きな特徴です。
メリット
・収入の安定性が高い: 公務員給与体系のため、一定のキャリア年数に応じた昇給が期待できます。 年収は約430〜450万円が目安で、役職に就けばさらに高収入となる場合があります。
・充実した福利厚生: 社会保険や退職金、厚生年金などがしっかり整備されています。
・労働環境の安定: 勤務時間や休暇取得の管理が徹底されており、過重労働の心配が少ない傾向にあります。
デメリット
・採用試験が必要: 公立保育士として働くためには自治体が実施する地方公務員採用試験を受けて合格しなければなりません。競争率が高く、試験準備に時間がかかる場合があります。
・配属先の異動がある: 同一自治体内であれば、数年ごとに異動を命じられる可能性があります(通勤範囲が広がるケースも)。
私立保育士の特徴
一方、「私立保育士」は社会福祉法人や学校法人、または認可外施設などの経営母体で働く保育士を指します。給与やキャリア形成は施設ごとに大きく違います。
メリット
・採用のハードルが低い: 自治体の公募試験が不要で、比較的早く就職できることが多いです。
・職場選びの幅が広い: 施設によって方針や運営スタイルが違うので、自分に合った保育理念や職場環境を選びやすいです。
・役職のチャンスが豊富: 一部の施設では役職に早い段階で就けることもあります。
デメリット
・給与幅が広く不安定: 年収は施設ごとに違いますが、350〜380万円が一般的です。一部、高待遇を提示する施設もあるものの、安定性にはやや欠けます。
・待遇が施設次第: 福利厚生の内容が施設によって違い、公立保育士ほどの手厚い制度を享受できない場合もあります。
公立と私立|給与比較
公立と私立の保育士での給与や待遇を比べると、公立保育士の収入の方が高い傾向にあります。以下の表で簡単に比較してみましょう。
| 項目 | 公立保育士 | 私立保育士 |
| 平均年収 | 約430〜450万円 | 約350〜380万円 |
| 福利厚生 | 手厚い(地方公務員準拠) | 施設による(対象外あり) |
| 昇給制度 | 昇進ごとの確実な昇給 | 施設の裁量次第 |
| 採用方法 | 地方公務員試験 | 面接や書類選考 |
公立保育士が向いている人
・収入や福利厚生を最優先したい方:
将来の安定性を重要視するなら公立保育士がおすすめです。地方公務員の昇給制度や年金制度により、生涯の収入計画を立てやすくなります。
・学力試験に自信がある方:
地方公務員試験に合格するためには計画的な勉強が必要です。試験準備ができる方にはおすすめできます。
私立保育士が向いている人
・自分に合った環境で働きたい方:
施設の雰囲気や保育方針を重視したい人には私立保育士がおすすめです。特に小規模園や個性豊かな園では柔軟な働き方ができることも。
・すぐに現場経験を積みたい方:
採用の敷居が低いため、短期間で経験を積みやすいのが私立保育士の特徴です。
どちらを目指すべきか?
「公立と私立、どっちがいいんだろう?」と迷う方も少なくありません。最終的には、自分にとっての優先順位(例:収入・待遇・働きやすさ)を明確にすることが判断基準です。
例えば、
・「安定した収入を軸」に考える場合:自治体の試験に挑戦して、公立保育士を目指す。
・「自分の理想とする保育方針を優先」する場合:多様な選択肢のある私立保育士を検討する。
良い条件で働きたいのであれば、事前の情報収集や施設見学を通じて、自分にぴったりの職場を見極めることが重要です。
派遣保育士、選択肢としてどう?
保育士として働く上で、「派遣」という働き方が選択肢にあることをご存じでしょうか?正社員やパートではない派遣保育士。近年では、働き方の多様化によって柔軟な労働条件を選べる派遣保育士のニーズが増えています。
派遣保育士として働くメリット・デメリットを整理することで、あなたにとって最適な働き方かどうかを判断しましょう。
派遣保育士で働くとは?
「派遣保育士」とは、人材派遣会社に登録し、その会社を通じて保育所や幼稚園で働く形態を指します。雇用主は派遣会社であり、派遣先の保育施設で働くことです。
派遣保育士の大きな特徴は、働く期間や時間を自分のライフスタイルに合わせられる柔軟性にあります。契約期間があるため、一つの職場に縛られることが苦手な方にも向いている選択肢です。
派遣保育士の平均時給と年収
派遣保育士は働いた時間に応じた時給が支払われます。フルタイムかパートタイムかで年収に幅がありますが、時給が正社員やパートより高めに設定されていることが多いです。
・平均時給:1,200円~1,800円
・年収の目安(フルタイム勤務の場合):約300万~360万円
派遣保育士のメリット
- 柔軟な働き方ができる
- 自分の都合に合わせて勤務日や時間を選べる点が最大のメリットです。
- 例えば、「週3日だけ働きたい」「午前中のみ」「短期間だけ働きたい」といったニーズにも対応可能。
- 高時給で働ける
- 派遣労働者の「同一労働同一賃金」の適用により、時給がパートよりも高く設定されるケースが多いです。
- 正職員よりも高い時給を目指せる可能性もあります。
- 残業や持ち帰り業務が少ない
- 派遣保育士は残業や家庭に持ち帰る仕事が少ないのもポイントです。
- 決まった時間に帰宅できるので、家庭や趣味との両立が図りやすいのも魅力的。
- 派遣会社のサポートがある
- 職場で困ったことがあれば、派遣会社が間に入ってサポートしてくれるので安心です。
派遣保育士のデメリット
- 雇用期間が限定的
- 派遣契約は基本的に期限付き(3ヵ月・6ヵ月・1年など)であるため、安定して同じ職場で長く働くのは難しいです。
- 特に気に入った職場でも契約が終了すると新しい派遣先を探す必要があります。
- ボーナスがない場合が多い
- 年収換算すると、正社員よりも少ないケースがあります。賞与が支給されないため、長期的に見て収入が伸び悩むことがある点に注意。
- キャリアアップの機会が限定的
- 基本的にクラス担任を任されることは少なく、保育補助が中心となるため、リーダーや主任などへの昇進は望めません。
- 長期的なキャリア形成を目指している人にとっては物足りない可能性があります。
派遣保育士が向いている人
・柔軟な働き方を優先したい人
家庭や他の仕事と両立したい、特定の曜日だけでも働きたいといった希望がある方におすすめです。
・短期間だけ働きたい人
長時間・長期間勤務が難しい状況やライフイベントに合わせた働き方が可能です。・固定の人間関係が苦手な人 派遣は業務範囲が明確なため、職場で深い人間関係を築かなくても仕事を進めやすい環境にあります。
派遣保育士の未来|需要の高まり
保育士の人手不足や働く環境改善の動きに伴い、派遣保育士の需要は伸びています。特に、柔軟な働き方を求める現代の潮流と多様な施設のニーズに応じて、自分に合った働き方を選びたい方に非常に人気が高まっています。
まとめ
派遣保育士は、自由度の高い働き方と高時給という魅力があります。一方で、長期的なキャリア形成や収入の安定には一定の制約が伴うことに注意です。自分がどのようなライフスタイルを送りたいかを考えた上で、選択肢のひとつとして検討してみてください。

令和の時代、保育士の未来
少子化や働き方の多様化が進む令和の時代、保育士を取り巻く環境も、これまで以上に大きく変化しています。これまで課題とされてきた給与の低さや長時間労働についても、少しずつ改善の兆しが見られるようになってきました。
では、これから保育士という仕事がどのような方向に進むのか、その未来について考えてみましょう。
給与アップの可能性
ここ数年、政府や自治体は保育士の給与改善に取り組んでいます。例えば、以下のような施策が実施されています。
・保育士の処遇改善加算:
経験年数やキャリアに応じて月額数万円の加算措置が導入されています。特にキャリアアップ研修を受けた保育士は専門職や管理職に就きやすく、給与が大幅に増える機会も生まれています。
・特例措置による給与上乗せ:
2022年、政府は一時的に3%(月約9,000円)の給与増加を実現するための補助金を支給しました。このような加算措置が恒久化される動きもあり、影響は今後続く可能性があります。
保育士の給与は少しずつ増加しており、今後もさらに改善が期待されています。
多様な働き方の実現
これまで保育士はフルタイムの正職員として働くのが主流でした。しかし近年、多様な働き方が広がっています。以下は新しい働き方の例です。
・派遣保育士:自分のライフスタイルに合わせて働けるため、育児中や短時間勤務を希望する人たちにも人気です。
・フリーランス保育士:個人契約で教育プログラムや子どもの一時預かりを請け負う新しい働き方が注目されています。
・テレワークとの融合:保育士に直接関わる仕事ではありませんが、幼児教育関連のテレワーク業務(教材開発、リトミック指導のオンライン講座など)も増加傾向にあります。
自分に合った働き方を選ぶことで、より充実したキャリアパスを描けるようになりました。
保育の質を高める技術革新
保育業界でもICT(情報通信技術)の導入が進んでいます。これによって業務効率化や保育の質向上が期待されています。
・日誌や連絡帳のデジタル化:
保育士の日々の業務である日誌や連絡帳をデジタル化する施設が増えています。書類作成の手間が減り、保育の時間がより子どもたちに集中できるものとなっています。
・見守りロボットの導入:
カメラやセンサーを利用した見守りロボットが導入され、保育士が遠くからでも子どもの状態を確認できるような環境が整いつつあります。
・教育プログラムの多様化:
AR(拡張現実)やVR(仮想現実)を活用した教育プログラムが保育の現場にも応用され始めています。子どもたちにとってより魅力的で学びやすい環境が提供されています。
これらの技術革新は保育士の負担軽減のみならず、保育そのものの質向上にも寄与しています。
保育士不足の解決に向けた動き
保育業界は慢性的な人手不足問題を抱えています。社会的なニーズの高まりを受けて、国や企業は以下の解決策を進めています。
・人材確保のための待遇改善
給与の増加はもちろん、新卒保育士の待遇をアップするような施策が進められています(例えば、奨学金の返済免除制度など)。
・潜在保育士の復職支援
保育士資格を持ちながら未就業の「潜在保育士」を対象にした復職支援策が充実してきています。ブランクがあっても安心して復職できるよう、研修制度を整える施設が増えています。
・外国人保育士の受け入れ
国際化が進む中、外国人保育士による多国籍な子どもたちのケアや英語教育を求める家庭が増えています。多文化交流の場としての保育施設の価値が高まっています。
将来のキャリア形成への支援
職場環境の向上やキャリア形成支援の取り組みも進んでいます。保育士には「ずっと現場で保育をする」という選択肢だけではなく、園運営や教育指導者として働く道も広がっています。
・園長や主任保育士への昇進
保育士経験を活かし、管理職を目指せる環境が整ってきています。
・専門講師や教育プログラムの作成
海外の事例をもとに新しい保育カリキュラムを導入する講師や教材開発の仕事も注目されています。
・大学や専門学校での講師活動
保育士経験者が次世代の保育士を育成する立場で活躍するケースも増えてきています。
未来に向けて、保育士が選べる道は広がる
保育士という仕事は、一人ひとりの子どもたちに安心感や成長を与える、非常に価値の高い職業です。職場環境や待遇についての課題も挙げられますが、時代の流れと共に少しずつ改善されてきています。
この記事でご紹介した情報を、今後のキャリアや働き方の選択肢を増やしていく参考にしていただければ幸いです。自分に合った未来像を描き、行動に移してください。
まとめ
保育士という職業には、子どもたちの成長を支える重要な役割がありますが、その反面、給与や働き方に関する課題も少なくありません。しかし、近年の制度改善や柔軟な働き方の普及によって保育士としての働き方の選択肢や年収を向上させる方法は確実に広がっています。
本記事の振り返り
- 保育士の現状と平均年収
保育士の平均年収は約382万円。年齢や施設の種類、役職によっても大きく変わります。特に公立保育士は安定性の高い収入を得られる可能性があり、私立は施設次第で幅広い選択肢があります。 - 多様な働き方の広がり
フルタイム勤務の正職員だけでなく、派遣やパートなど、ライフスタイルに合わせてフレキシブルに働ける環境も増えつつあります。特に派遣保育士は高時給で効率よく働ける選択肢として注目されています。 - 令和時代の保育士の未来像
少子化や技術革新が進む中、保育士はより重要な存在として位置付けられています。より効率的で質の高い保育が求められる中で、待遇改善やキャリア形成の選択肢は拡大しています。
今日から始められること
保育士として年収アップや働きやすい環境を手に入れるため、次の一歩を踏み出してみませんか?
- 【転職を考える】自分に合った施設や働き方を得られる求人サイトを活用する。まずは情報を集めましょう。
- 【資格取得を検討】リトミックや児童発達支援管理責任者などの資格取得に向けた第一歩を踏み出しましょう。
- 【相談する】保育士に特化したエージェントやキャリアコンサルタントと話して、現状を見直す機会を作ってみましょう。
保育士はただの職業ではありません。子どもたちの人生の基盤を築く大切な存在であり、同時に、その仕事を通じて自分自身の成長や幸福感を得られる素晴らしいキャリアです。ぜひ、自分に合った道を探し、さらに輝ける未来を築いていってください!